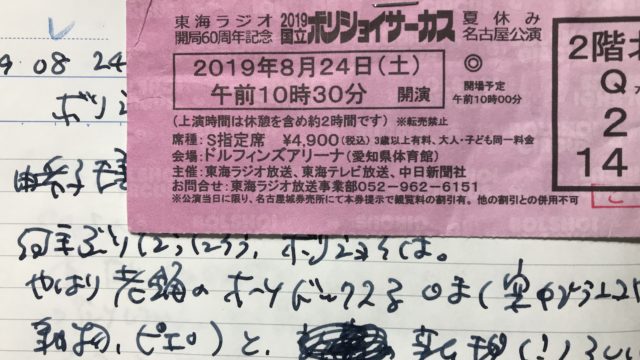変幻自在 縦横無尽 84歳はコロナも作品に
(愛知県美術館、2021/1/15~4/11、2/10鑑賞)

なんというごちゃまぜなんだと振れ幅に脳を揺すぶられていたら、ここまで突き詰めるのかという凝視の世界があらわれて目が点になる。3往復してたっぷり刺激をもらい会場を出たら、コロナを題材にしたマスク作品が待っていた。縦横無尽の84歳、横尾ワールドの2時間を堪能した。
■ポップなポスター ほんの一部
ぼくにとってこの作家は「ポップで斬新なポスター」の印象が強かった。一見すると不釣り合いな写真やイラストとキャッチーな言葉とが破調をはらんで組み合わせてあり、全体の構成も型破りだった。だからこそずっと記憶のどこかに残ってきた、とみてきた。
ところが会場に入ると、ポスター仕事はほんの一部でしかないことがすぐわかる。表現はイラストから大きな額縁つきの油絵、アニメーション、写真、インスタレーションへと広がっていた。展覧会には直接出てこないが、本もたくさん書き、最近は朝日新聞文化面に大胆びっくりの書評も寄せている。
■ひとくくりのコトバが見つからない

会場をひと回りした後、頭に浮かんだ言葉をランダムに記してみた―。
サイケ、夢、狂気、熱情、幻想、超現実、世紀末、乱視、奇想天外、原色、非対称、エログロ、土俗、回帰、幼児性、宇宙……
どの言葉も浅くて、中途半端だ。ひとくくりにできる概念や言葉が見つからない。2002年個展で使われた『森羅万象』は当てはまるだろうが、それは平たく言えば「何でもあり」だ。そもそもこの人の仕事を言葉でまとめようとする無意味さを味わうしかなかった。
■滝のポストカードが1万3千枚 !
そんな「ごちゃまぜ」「何でもあり」の広がり感あふれる展示の中で、異彩を放っていたのが滝のポストカードだった。大と中の壁に1万3千枚が張り詰めてあり、万華鏡のようなインスタレーションになっていた。
説明パネルによると1988年から5年ほどモチーフとして滝に魅せられ、世界各地の滝の写真を集めたのだという。確かに滝をテーマにした絵も展示されているが、目はすぐにカード1万3千枚にいってしまう。うーん、この入れ込み方と収集、やっぱり半端ないなあ。
■肖像図も自在に375枚 和田・山藤と同学年
もうひとつぼくがおおっと声を上げたのが、壁一面の「肖像図鑑」だった。「撮影可能」と表示があったのもうれしかった。

文豪から画家、俳優、音楽家、陶芸家、評論家…。著名な表現者たちの肖像画が一列に6人ずつ並んでいる。その数375枚。瀬戸内寂聴の新聞連載『奇縁まんだら』の挿絵から始まったシリーズと説明されていた。

ここでも画調は変幻自在だ。取り上げた人物の表情も構図も色づかいも輪郭線も、これっといった決まったスタイルはない。このあたりは横尾と同学年の描き手と比べてしまう。
そのひとりは故・和田誠(1936年4月生)だ。似顔絵では、ぼくが一番好きな描き手である。絶妙なる単線を生命線にしていた。wikipediaによれば、横尾は30代後半、東京五輪のころに和田と知り合っている。
もうひとりは山藤章二(1937年2月生)。週刊朝日を舞台に独特のデフォルメと言葉で異次元の面白さを引き出してきた。もしかしたらと思ってネットで生年を調べたら、なんと同学年だった。
面白いなあ、この3人が同学年だなんて。それに3人とも、仕事も人物も生き方もなんて魅力的なんだろう。
■「Y字路」シリーズ 反復と変奏
2000年以降の作品で欠かせないキーワードとして「Y字路」が出てきた。故郷・西脇市の三叉路にあった模型屋さんが原点という。あちこちの三叉路が、場所や時間を変えて繰り返し描かれている。
説明には、このシリーズから感じ取れる感覚として「既視感とよそよそしさ」「現代日本の闇に浮かぶ昭和的世界の亡霊」「反復と変奏」とあった。うまいことすくい取るなあ。企画展テーマ「原郷」とも通じている。
■場外に『WITH CORONA』マスクで赤んべえ


入り口に戻って最初から見直すこと2回、さすがに堪能できて出口を出たら、また仰天させられた。自分の過去の作品などにマスクをコラージュした「コロナ禍の新作品」が、通路両脇の壁ガラスにびっしりと貼ってあるのだ。白いマスクには、赤い舌と唇の「あかんべえ」が描かれている。
昨年の5月末からツイッターやブログで発表を始めたという。マスクはコロナと2020年を象徴するアイコンである。
それをモチーフにして自作や著名人物を「変奏」させて現代とからませ、あかんべえで社会との距離もとってみせる。トランプも使ったツイッター上で展開するー。これがこの画家の「現況」なのだろう。この同時代性、すごい。
■館長みずから企画 さすがの評論
この展示会は愛知県美術館の現館長、南雄介氏がみずから企画した。そのことを2月4日朝日新聞への寄稿文で知った。2002年の『森羅万象』展でも企画に携わっており、作家・横尾の特質をこう表現している。
- 千の顔を持つ画家 / 芸術的多重人格者
- スタイルに対する自由な態度
- 直感と偶然を導きの糸とする
- 自らの肉体の声に耳を傾け、魂の求めに従った
展示会を観終わったいま、これが的確な表現であることがよくわかる。この訪問記の冒頭でぼくは、最初にひと回りした時の印象が散漫な言葉の散らばりにしかならず、ひとくくりにできないと自嘲気味に書いた。でもこの作家はそれでいいのだろうとも思っていた。事前にこの文章を読んでいたからだ。
展覧会のタイトルに「原郷」「幻境」「現況」という同音異語を配した着想とセンスにも拍手を送りたい。横尾忠則の展覧会では過去最大級だそうだ。コロナ関連作にもみられる大胆な展示ができたのも、館長みずから企画した展示会だったからだろうか。ひとりの現代作家に絞り、これだけ見応えのある作品をたくさん集めた展覧会をここ名古屋で観られるとは期待していなかった。すごくうれしく、誇らしい。
(付録)
■森喜朗氏は1歳下 生き方と評価の違い
いまお騒がせの東京五輪組織委会長の森喜朗・元首相は1937年7月の生まれの83歳。横尾忠則、和田誠、山藤章二ら3人のひとつ下の学年である。
森氏は3日の女性蔑視発言で引責辞任に追い込まれると伝えられているが(2/11日時点)、あの発言は本人が4日の会見で自虐的に言ったように「老害」ととるべきではないと思う。年寄りになったので判断力が鈍ったという話ではないだろう。
ぼくの見方では、あの発言は森氏の人格と生き方からにじみ出ている。あの場であの発言ができる(できてしまう)政治家だったからこそ、自民党三役から文部・通産・建設の3大臣、さらには総理大臣まで歴任する「華麗な政治キャリア」を重ねることができたのだと考えている。
当時の政治や自民党はそれを求め、許す世界だったのだろう。それを生んだ原因のかなりは国民の投票行動とメディアの政治報道にもある。
森氏より年がひとつ上の横尾画家は、コロナ禍でもベッド上から懸命にアップデートな作品を発表し続けている。過去のスタイルや常識にとらわれない姿勢は、こちらも従来からのもので、それがあるからこそこれまでの画業と今日の彼があるのだと思う。
80歳を過ぎてからの評価の違いは、政治家と画家の違いかもしれない。描き手の3人がいま森氏を描くとすればどんな肖像画や似顔絵になるのだろうか。ぼくはひそかに想像して、にやにやしている。