診療→井戸→用水路 不屈の突破力 たやさぬ含羞
(撮影・監督=谷津賢二、9月4日、名古屋・シネマスコーレ)
福岡生まれの医師・中村哲のドキュメンタリーだ。38歳で日本を飛び出し、パキスタンとアフガニスタンで貧しい山村への援助に全霊を捧げ、2019年に何者かの凶弾に倒れ73歳で死亡した。診療だけでは救えないと井戸掘りを始め、干ばつ飢餓に直面すると用水路建設に突っ込んでいく。すぐわきでカメラを回してきた日本電波ニュース社の映像は、病や貧困の大本に迫る不屈の突破力を伝えている。なのに朴訥とした口調と含羞を絶やさない振る舞いに、ぼくは涙ぐんでしまっていた。

■より困難な道へ飛ぶ選択
中村医師は1946年9月に福岡県で生まれた。団塊の世代のトップランナーで、ぼくより6歳上だ。その活動は自著の広告、テレビ番組、国会出席や講演のニュースで知ってはいた。しかしどれも断片的だった。
このドキュメンタリーで初めて全体像を知った。まず驚いたのは中村医師の選択が、大事なことになるほど「より困難が予想される」方へとジャンプしてきたことだった。
① 38歳でペシャワールの病院へ
九州大学医学部を出て国内の病院に勤務後、1984年、パキスタン・ペシャワールの病院に着任した。その6年前、登山家としてこの国を訪れ、無医村でボランティア診療をした時の患者数と深刻度に衝撃を受けたことが要因になったと語っている。
38歳の医師が家族を残し、あえて設備も不十分なパキスタンの病院へ行き、未経験のハンセン病を担当する―。強い使命感がないと選べない選択だっただろう。
② 診療所だけでなく井戸も
苦労のすえアフガンに1998年、PMS(Peace Medical Services)病院を開設する。しかし2000年に大干ばつがアフガンを襲った。水もない生活から生じる病に医療はなすすべがない―。そこで中村医師やスタッフは、井戸を掘り始める。「見捨てちゃいけない、という以外に理由はない」

③ もっと農地をと用水路建設へ
しかし干ばつの被害は止まらない。食べ物さえ育てられなくなって村人は村を捨てはじめた。そこで中村医師は2002年、用水路をつくって砂漠を緑に変える計画をぶち上げる。
土木の専門家はいない。村の長老たちが異を唱える。中村医師が英語も交えて説得にあたる―。ぼくは大成功という結果を知っているから平静で観ていられるが、当時のスタッフはどきどきだったろう。しかし画面の中村医師は飄々としているのだった。
■書き言葉にも力 朗読は石橋蓮司
全編を通じ中村医師の書き言葉も挿入されていく。著作や、活動を支える団体「ペシャワール会」の会報から引用されている。朗読は俳優の石橋蓮司。渋くて重く、聴くものをとらえて離さない声だ。
人は必ず死ぬ。生命体として逃れられぬ掟である。
ここには、天の恵みの実感、誰もが共有できる希望、そして飾りのないむきだしの生死がある。
米軍ヘリから機銃掃射も
いちばん凄みを感じた引用は2003年の用水路建設シーンで出てきた。2年前の「9.11テロ」を受け米軍はアフガン空爆を続けていた。上空を通り過ぎる爆撃機を見上げながら中村医師が、少し前に機銃掃射を受け危なかったとさりげなく語ると、次の字幕と朗読が入る。
彼らは殺すために空を飛び、我々は生きるために地面を掘る。
飄々とした語り口からは想像しづらい豪直球だ。短いが見事に真実を貫いている。中村医師のwikipediaをのぞくと、戦前の芥川賞作家、火野葦平は母方伯父(母親の兄)だとあった。
中村医師の著作は読んでいないので推測になるが、こうした書き言葉の力も日本国内で支援者や寄付を集めるのに役立ち、ペシャワール会を通じ現地活動を支えていたのではないだろうか。
■あふれる含羞 信頼と支援の源泉か
実はぼくが、より魅かれたのは、中村医師の身なりや風貌、語り口やしぐさだった。

- 現地の男たちと同じ帽子をかぶり、口ひげをたくわえ、いつも粗末といっていいシャツやズボンをはいている。
- しゃべり方は朴訥で、もぐもぐしていて、明瞭とはいえない。
- 目に力はあるけれど、人に面すると伏し目がちになる。
- だれにも謙虚であろうとし、威圧的なところは一切ない。
ぼくは映像を見ながら、こうした面持ちや肌合いを表す言葉を探していた。思いついた日本語は「含羞」しかなかった。
現地への貢献度や、決断の大胆さと突破力との落差は大きい。しかしこの含羞と落差こそが、現地の人々を安心させ、この先生ならと信じさせてきたのではないか。日本の人たちに中村医師を支援したいと思わせてきた力の源泉にもなった気がする。
■21歳の時に訪れたアフガン
ぼくはアフガニスタンを1973(昭和48)年の10月に訪れている。大学の2年と3年の間に1年間休学してユーラシア大陸を放浪していた時だ。当時21歳。イランから入国し、ヘラート、カンダハル、首都カブールの簡易宿に2泊か3泊しながら移動した。

欧米人のバックパッカーと街歩きをし、食堂でパンや羊肉を食べ、紅茶を飲んだ。トルコやイランと比べるとはるかに貧しく、インフラも整っていなかった。ただ地政学的には文明の交差路にあるためか、美男美女が多く、色彩やデザインも繊細で高度な印象をうけた。
ところが5年後の1979年、ソ連がアフガンに侵攻した。撤退するのは10年後の1989年で、その年にはソ連邦が崩壊し、つい一昨日死去したゴルバチョフが退任した。1989年は、プーチンのウクライナ侵攻を考える際の鍵の年でもあろう。
中村医師がアフガンで医療活動を活発化するのは1990年になってから。PMS病院ができた1998年に、ぼくはタイに赴任し9.11テロの直前までバンコクにいた。その時点では恥ずかしながら、中村医師の活動は知らなかった。
■おぞましき輪廻 大国に翻弄されて
このドキュメンタリーを観てあらためて思う。アフガンは2001年の「9.11NYテロ」の後に米軍から空爆を受けた。ソ連撤退からまたも10年後、なんというおぞましい輪廻だろう。
それでも中村医師は空爆下でも用水路建設を続けた。敬服という表現以外に賞賛の言葉が見つからない。
そしていま、その米軍もアフガンを去り、タリバン政権が再び実権を握ったが、国際社会の承認も援助を得られていない。しかも激しい干ばつが続いて国民は困窮してしまっているという。
おぞましい輪廻はいまウクライナでも起きている。ぼくには、中村医師のあの言葉を再度かみしめ、冥福を祈ることしかできない。
彼らは殺すために空を飛び、我々は生きるために地面を掘る。
/200910-映画パンフ-scaled-e1602333444977-640x360.jpg)
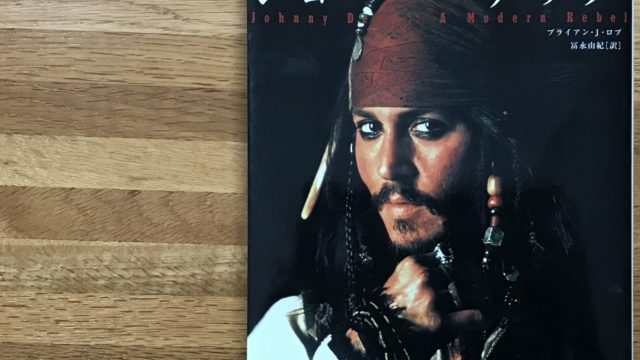
/IMG_7244-scaled-e1602332166584-640x360.jpg)
/IMG_65161-scaled-e1602333346661-640x360.jpg)


