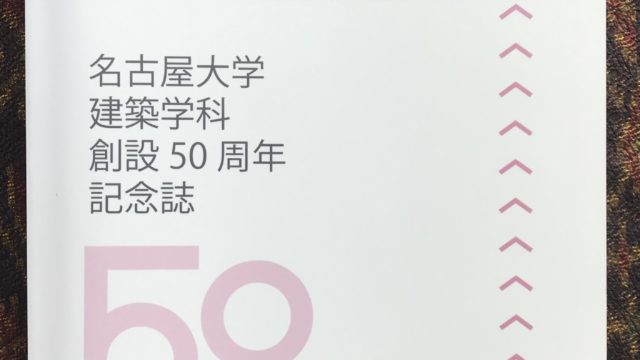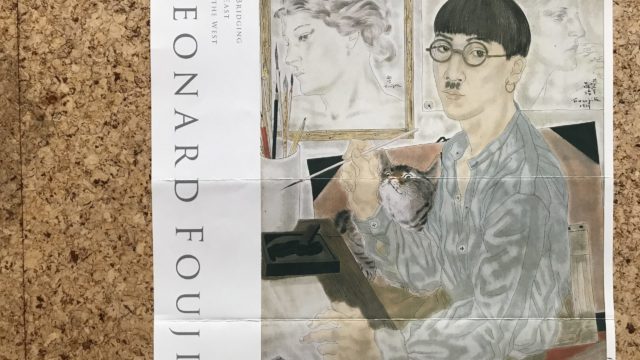作品 直言 映像 壁に挑む奔放 驚きの連続
(愛知県美術館、1月14日から3月14日)
この芸術家の印象はずっと、大阪万博で見た奇怪な『太陽の塔』、TV広告で流れた絶叫「芸術は爆発だ!」、漫画家と小説家の両親からもらった強烈な自我、の3点セットだった。しかし今回の「過去最大の回顧展」は新鮮な驚きに満ちていた。パリ留学と出征、活動領域の広さ、「爆発」だけでない直言、つき抜ける世界観…。「TARO」の情念がほとばしる会場は、ぼく自身の記憶を回顧する場にもなった。

驚き<1> オリエンタル中村 あのレリーフも
会場に入るとまず「岡本太郎と愛知」というコーナーがあり、大きなパネル(写真①)に息をのんだ。説明には「オリエンタル中村百貨店の外壁レリーフ 1971年、名古屋・栄に完成」とある。

えーっ これも岡本太郎だったの? ぼくは1970年夏に大阪万博で『太陽の塔』を見て作家の名を知った。このレリーフが完成した1971年は、舞鶴から名古屋へ出てきた年だ。都心の栄をぶらついた時にこのレリーフを見た記憶はあるけれど、なんと不覚にも、『太陽の塔』と同じ作者との認識はなかった。
なぜだろう。このレリーフは中村が三越傘下になると撤去されており設置期間は10年もなかったから? 近くの丸栄が巨匠・村野藤吾の設計で、東郷青児のエレベーター扉絵もカッコよく、中村の印象が薄かったから? レリーフのデザインも署名も、まぎれもなく「TARO」なのに…。
驚き<2> 留学10年 出征4年 父と同い年
次の「第1章 パリ時代」のパネル説明によると、岡本太郎は18歳だった1930(昭和5)年、父(漫画家の一平)と母(小説家のかの子)に同行してフランスへ渡り、両親の帰国後も残って約10年、パリで学んだ。
ちょっと待て、すると岡本太郎の生まれは明治か大正のぎりぎりだ。誕生日を確認すると1911(明治44)年2月だった。ぼくの父は明治43年11月の生まれ。この稀代の芸術家はなんと、父と同学年だった。

ぼくの父は京都・舞鶴の農家の長男として生まれ、2003年に舞鶴で死んだ。舞鶴から出たのは、大学に通った大阪での4年だけ。岡本太郎は芸術家になる星のもとに生まれ育った―。パリ時代の作品群(写真②)を観ながら思った。ところが「第2章 創造の孤独」のパネルにこうあった。
1940年、ナチス・ドイツによるパリ陥落の直前に帰国した岡本太郎は、戦時色が濃くなるなか召集を受け、中国で4年間にわたる過酷な軍務と収容書生活を経験する。1946年に復員したとき、東京・青山の自宅は渡欧作品もろとも戦火で焼失していた
戦争は何人をも地獄へ落としてしまう。岡本が戦後、再び精力的に描き始めたころの作品(写真③)には、暗い色調の作品が多い。戦争の影をみてしまうのは安易すぎるだろうか。

驚き<3> 溶ける領域 膨大な作品数
展示を5章まで見ていくうちに、表現の対象やタッチが微妙に変化していくのがわかった。活動の領域はどんどん拡がっていく。しかも、平面と立体、ふたつの領域が溶け合っていく流れに圧倒されていった。
油彩は、青春期には翳りを残しているように思えた。しかし最盛期になると曲線と原色が入り混じり、作家の熱であふれかえっている。晩年になると、黒くて大きな丸目がこちらをじっと眺めてくる。



写真もたくさん残した。スライドショーで映し出される作品は、秋田や青森、沖縄などの日本各地と、韓国やメキシコで撮影した土俗的な祭礼や、土地の人々の豊かな表情を切り取っていた。
1960年代後半に制作された『太陽の塔』と『明日の神話』では「巨大」にも挑んでいる。壁画の『明日の神話』(写真⑦)は行方不明だったが、発注元のメキシコで発見されて2003年に帰国、修復をへて2008年、渋谷駅の通路に設置された。『太陽の塔』の保存活用と並んで、「岡本太郎」の名を蘇らせ不動のものにしている。

作品リストによると展示総数は277。その大半が、フラッシュを焚かなければ撮影可能だったのも、感想記を書く気ででかけたぼくにはうれしかった。
驚き<4> 野太い言葉 言い切り直言

「第4章 大衆の中の芸術」には、岡本太郎が残した言葉を集めたコーナーがあった(写真⑧)。真正面の壁には黒地に白字でこうあった。
情欲に流されるのはいい。
だけど、流されているという
自覚を持つんだ。
その左横の壁には、白地に赤字でこうあった。
危険だ、という道は必ず、
自分の行きたい道なのだ。
もう少し進むと、言葉はもっと「自己」へと向かっていく。
自分の中にどうしても譲れないものがある。
それを守ろうとするから弱くなる。
そんなもの、ぶち壊してしまえ。壁は自分自身だ。
自我を強く意識したうえで、それを飛び越えて挑戦しよう、と叫んでいる。展示作品がそれを見事なまでに伝えてくれるから、うーん、とうなずいていた。
驚き<5> 時間を埋める 映像の力
会場には随所にモニター画面があり、岡本太郎が登場する映像が流れていた。NHKが主催団体に入っており、過去のアーカイブス映像から選択されているようだ。岡本太郎の生前のインタビューも壁面に投射され、たくさんの来場者が見つめていた(写真⑨)。

映像には公園に設置したオブジェの除幕式のニュースもあった。『太陽の塔』の工事風景はなつかしかった。『明日の神話』が渋谷駅に2008年に設置されるまでのドキュメントは、作品の大きさと里帰りへの興奮が蘇ってきた。
極めつけは「芸術は爆発だ!」だった。説明文によると、ビデオカセットのテレビ宣伝として作られ、放映は1981年ごろ。会場では「ピアノ編」と「釣鐘編」が流れていたが、悲しいかな、ぼくが覚えていたのは、あの叫びの場面だけだった。
驚き<6> 若年層にも人気 いまも起爆力
驚きの最後は、思っていた以上に観客が多かったことだ(写真⑩⑪)。ぼくは名古屋初日となった14日の午後に妻と訪れた。土曜日ということを割り引いても、 こんなに人気があるのかと驚いた。

もちろん岡本太郎はいまも日本でもっとも著名な芸術家のひとりだろう。この「過去最大の回顧展」は昨年、まず大阪と東京で開かれた。名古屋開催を待ちわびていた美術ファンも多かったに違いない。

しかも、デートらしい二人連れもかなりみかけた。ぼくからすると孫のような初々しい男女がかるーく手をつなぎながら、情念たっぷりの作品の前でマスク越しに何かをささやきあう様子をながめるのは、いいものだ。
小学生の子をつれてきた家族も何組かいた(写真⑫)。不思議なオブジェの前でポーズをとっている男の子もいた。こちらもうれしくなった。

これはきっと、岡本太郎の作品にはいまも、若い人たちに訴える起爆力と大衆性があるからに違いない。ほとばしる創作欲と反骨心は勇気や元気をくれる。正と反を一緒に織り込み、化学反応を視覚化する大胆な表現は、いまもスリリングだろう。
ぼくが名古屋で最近観た展覧会で、若い人たちが似たような反応を示すのを見たのは、2021年の『横尾忠則展』と『バンクシー展』だった。彼らはまだ健在だが、岡本太郎は1996年に84歳で死去してからもう27年になる。
回顧展のこの人気は「死して、なお」なのか、「低成長にあえぐ時代だからこそ、なお」なのか―。どちらでもある気がする。