キャップが語る現場 取材と原発問題
(2011年4月20日)
【注】NIMRAはぼくが加入する私的異業種交流会「名古屋国際都市問題研究会」の略。幹事をつとめた2011年4月例会の報告を、講師をお願いした鈴木孝昌氏の承諾を得て公開します。過去の例会報告はHP (http://www.nimra.jp/index.html)でも閲覧できます。当時の新聞記事は縮刷版から抜粋しました。
4月例会は中日新聞社社会部の鈴木孝昌部次長に「東日本大震災を考える 新聞報道の立場から」と題して講演をしてもらった。鈴木氏は、中日新聞に1985年に入社後、本社経済部、社会部で幅広く取材を経験。この間、北京と香港で通算9年間にわたり特派員もつとめた。
今回の東日本大震災では、本社内で取材の取りまとめ役をつとめ、10日目からは現地取材班キャップとして宮城、岩手で取材の指揮をとった。この震災は「戦後最大の日本の危機」だけに、参加者は21人といつもの倍。円形に座っての自由論議も熱っぽいものとなった。以下は講演の要約です。(文責:団野誠=幹事)
【鈴木氏の講演の要旨】
震災が発生した午後2時46分というのは、新聞社にとっては夕刊が終わって一日で一番ほっとしている時間でした。巨大な津波が街を飲み込んでいく様子を、ヘリからの生映像を通してテレビが生中継した。世界で初めてのことで、衝撃だった。

こうした突発的な出来事の取材体制をどうするか決めるのが私の仕事。中日は被災地には支局がないので、近くにいた記者4人をすぐに小牧に向かわせ、社有のヘリで福島に飛んでもらった。
スーツに革靴。コートも着替えもなし。翌朝には仙台・若牧地区や石巻、陸前高田などに入った。記者とカメラマンはピーク時は27人を送り込んだ。
記者によると、現場は凄惨のひとことだった。一面が海水とがれき。がれきの一部のようにたくさんの遺体があった。9割が水死。損傷は少ないが、全身が泥で汚れていた。

なんとか避難した人たちの隣に、たくさんの遺体がある。最初に現場に入った記者たちは被災の規模が大きすぎて、自分は全体像を伝えられるのかと立ちすくんでいた。私は「目の前にあることをそのまま書いてこい」と励ました。
私も1週間後から現地キャップとして被災地に入った。ある遺体安置所はボーリング場だった。レーンに化粧飾りのついたお棺が並べてあった。遺体の顔もきれいに拭いてあった。遺体の尊厳を守る日本の意識を感じた。若い母親が行方不明の我が子を探していた。この棺の遺体が自分の子であってほしくない、でも、探したい。そんな意識だったろうか。ついに見つけると、ただ泣き叫んでいた。「ごめんね、ごめんね」と。
被災者の皆さんは、取材に対して、当初は他市や他県の被災の状況を知りたがった。しかしメディア関係者は全部あわせると数万人に達した。やがて被災者との間に摩擦が生まれ、時には被災者にしかられたり、けんかになったりしたこともあったらしい。
福島原発は(現場に入れないため)東電、保安院、官房長官などが1日に2、3回ずつ行う発表が情報のほとんど。東電は会見の内容もおそまつで危機管理能力のなさを露呈した。放射能の拡散を調べる「スピーディー」もなかなか公表されず「隠ぺい体質」を感じた。
その放射能については、紙面化の際、余計な不安を巻き起こしたくないとの意識はあった。ただ当局の「直ちに健康には被害はない」との説明を、おかしいと書けるだけの力やデータがこちらにないのも事実。どのくらい浴びたらどんな病気になるのかというデータが広島、長崎くらいしかないとも聞く。
原発関係の記事でいちばん反響があったのは、福島での現場作業を嫌って名古屋へ避難してきた元作業員の証言を大きく書いた時。作業の実態がよくわかったという声と同時に、逃げてきたやつの話をどうしてこんなに大きく書くんだという批判もいただいた。
【幹事からひとこと】
期待以上の参加者数と熱い議論になりました。質問や論議が原発に集中したのは予想通り。原発の将来をめぐる問題が佳境に入って「朝まで生テレビ状態」(鈴木氏)になりかかったところで時間切れになりました。原発をどうするかは、日本人ひとりひとりが自分の問題として考え続けなければならない問題だと思います。

/IMG_7269-scaled-e1603003962398-640x360.jpg)

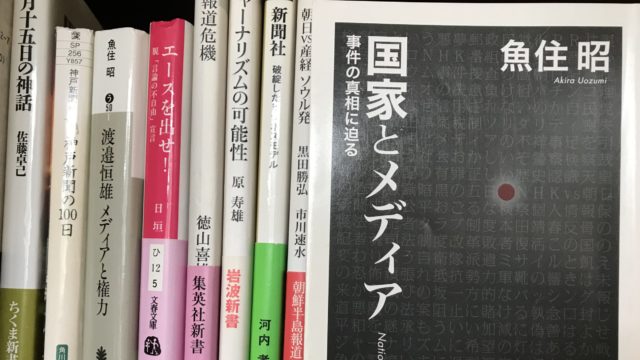

/IMG_6940-scaled-e1602332742445-640x360.jpg)
