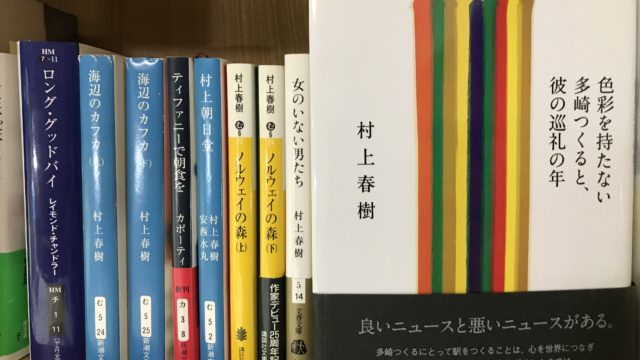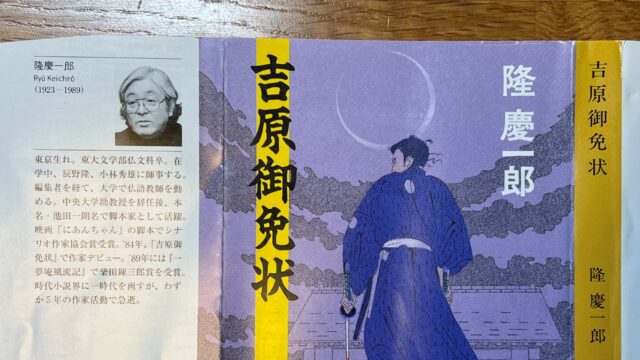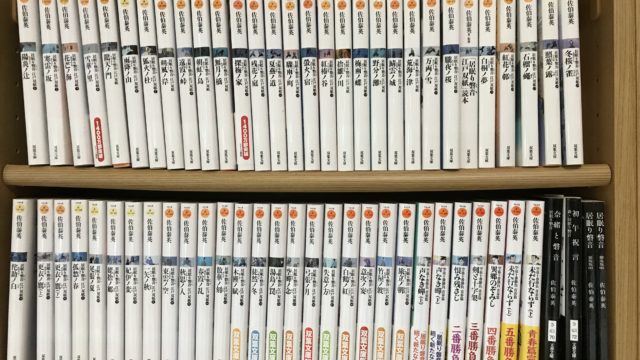笑いの神髄求め 文学に到達してるか
(文藝春秋、2015年9月号)
ことし前半の芥川賞である。「現役の芸人が書いた純文学」として大変な話題になった。受賞時のニュースや書評では、漫才や笑いと正面から向かい合って書かれているとあった。その通りであった。

主人公が師と慕う先輩は漫才においては天才肌であり、理想追求型の理論派である。その一方では性格的に一途で妥協性がなく、金銭感覚に乏しい。
ふたりの10年にわたるつきあいや漫才が交錯しながら進むが、軸足はやはり漫才やコントが受けるということの意味は何か、にあるのだろう。
ただ残念ながら、芥川賞だからと期待したほどの感銘は得られなかった。師匠と仰ぎ見る天才との交情や笑いの本質とは何かという追及が、純文学にまで昇華しているとはぼくには思えなかった。ほかの候補作を読んでいないので、遠い外野席からの観戦記にすぎないけれど。
実は直木賞の東山彰良『流』にも似たような感想を抱いた。芥川・直木賞に選ばれれば、好き嫌いは別にして、質の高さは保証されているはずだ。それなのにぼくがそれをわからず楽しめないのは、実にもったいない。感性が鈍って時代遅れになりつつあるらしい。ただシニカルなだけの辛口読み手に傾いているのだろうか。気をつけないといけない。
筆者は現役のお笑いタレントで、高校時代は強豪校のサッカー選手だったとの経歴は新聞記事で知って、ぼくもすごく驚いた。35歳のまだ若い芸人がこんな派手な作家デビューをしたことには、ちょっとうれしくなった。
そうした横顔と芥川賞との意外で新鮮な組み合わせが、200万部を超すとてつもないベストセラーにつながっているのだろう。漫才やコントがテレビで流れていてもいまはほとんど観ないけれど、この現象の背景はわかる気がする。