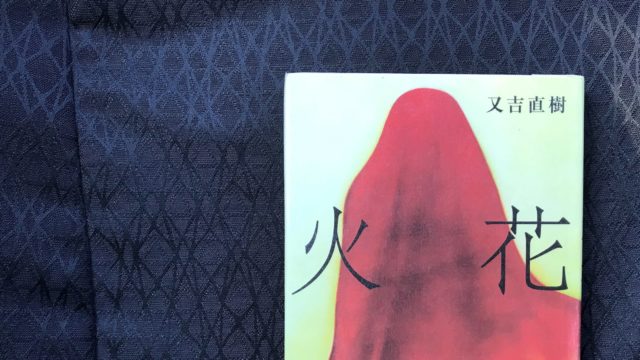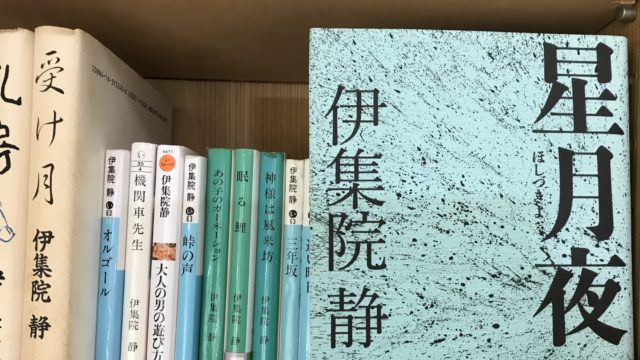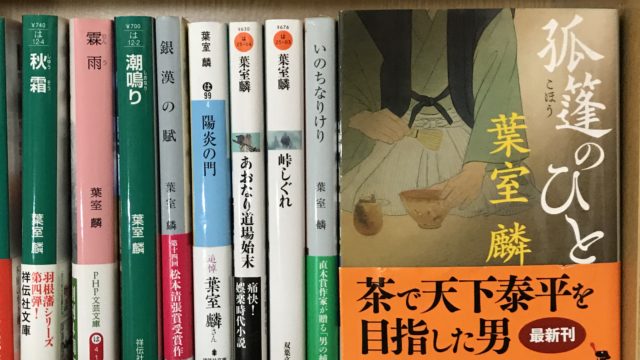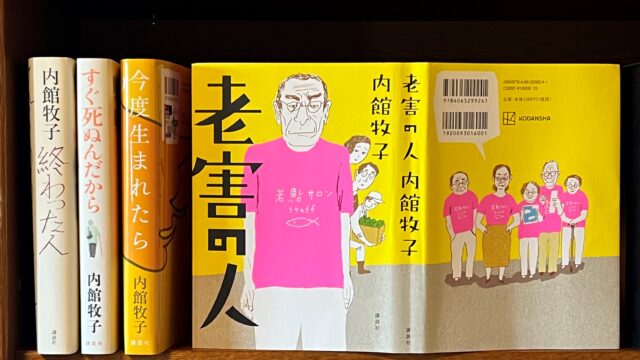あのインドの匂い 輻輳してぼくを呼ぶ
(新潮社、2018年)
ことしの芥川賞。インドが舞台ということにも魅かれて読んだ。

読み進むにつれて、あの国の様子がありありと浮かんでくる。混とんと臭い、エネルギー、猥雑とむせ返り、騒音、他者への無関心、貧富と差別、天才たちの群れ…。
本の中にはまた、ぼくが20歳のときの貧乏旅行で肌で感じたインドの感触があった。50歳近くのバンコク特派員時代に取材で訪ねて頭でとらえ直したインドも出てきた。いくつかの映画でわくわくしたインドも書いてある。
いくつものインドの印象が重なり合って、ぼくの中でよみがえった。そうした印象を包む空気が、本のあちこちに流れているではないか。
この小説ではまた、非現実的なシーンと時間軸が、妙にリアルな描写と交錯するので、なんとも不思議な気分になる。
万人受けする小説ではないだろう。選考にあたった著名作家たちが、自分にはない、新しいにおいがする作品をという意識で選んだ結果のような気もする。
その意味では、この選考は、日本の暮らしや文化に淀む閉塞感をにじみ出させている、と理屈っぽくはいえる。
ネットによれば、筆者は早大法学部を卒業後、様々な職業を経てから東大大学院でインド仏教を学んだ女性だ。いまは日本語教師としてチェンライ(マドラス)に住んでいる。かなり異色のキャリアといっていい。
そもそもインドを舞台にした日本人による日本語の小説というと、ほかにあったのだろうか。