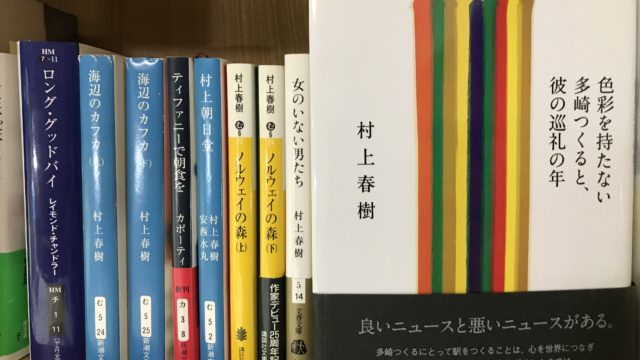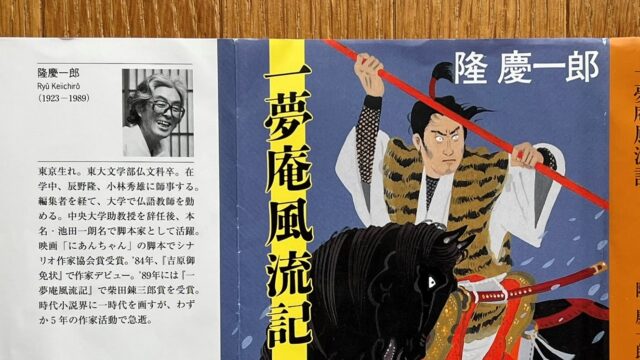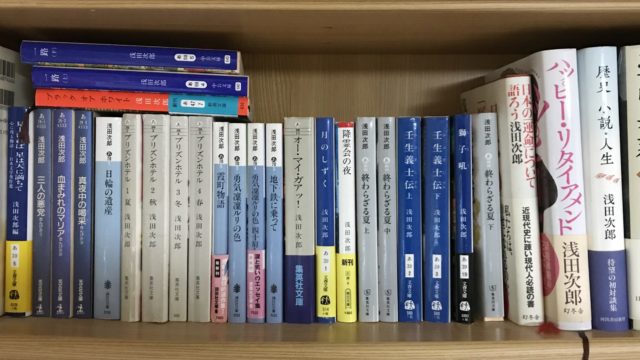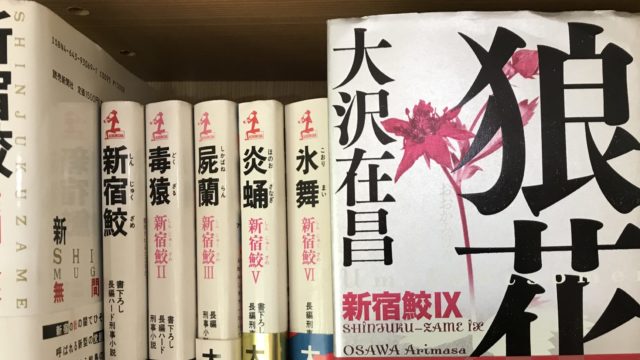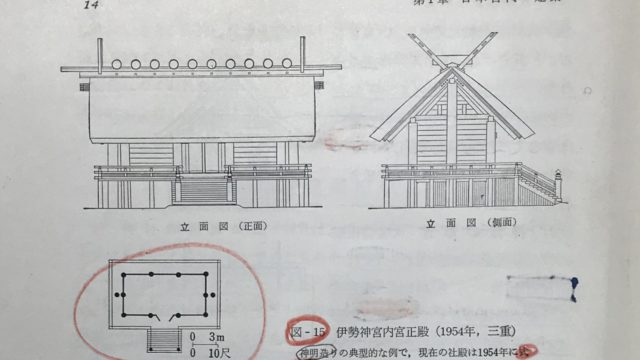名古屋の街の青春と事件 88歳に疼く戦争
昭和7年生まれの88歳、故郷名古屋シリーズの第2巻が2020年ミステリー国内部門で3冠-。こんな魔力的な惹句に誘われて年末に第1巻、お正月に第2巻を読みふけった。米寿になってもこれだけの筆力と熱量を保つ先達がいて、しかも理不尽な戦争への怒りが今もたぎっている。20年も若輩で戦後生まれのぼくはいま、驚きとうれしさに呆然としている。
(ともに東京創元社、2018年8月/2020年5月)
<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます
帯の略歴によれば、作者はアニメ脚本やミステリー作家として長いキャリアを重ねてきた。「三冠」「最高齢88歳」「レジェンド」のコピーも並んでいる。大学の先輩であり中日文化賞も受賞されているから名前は知っていたけれど、アニメには食指が動かないまま今日に至ったこともあり、恥ずかしながら、きちんと作品に触れるのはこれが初めてだった。
どちらの作品も序盤から中盤は、当時の青春群像や名古屋の街がのびやかに、しかもとても絵画的かつ具体的に描かれていく。殺人事件が発生しても、アニメ作品を文字で読んでいるような軽さやユーモアを伴ったままだ。これが終盤になると、事件の背後にはあの「戦争」の毒気がどす黒く渦巻いていることがあらわになり、作品は一気に骨太になる。
■昭和12年版は博覧会 昭和24年版は男女共学
筆者は昭和7年の生まれだから、もっとも多感な時期に戦争が日常になっていったと想像する。第1巻の昭和12年版は、春に名古屋で開かれた国際平和博覧会が舞台だ。筆者は当時5歳だから、親に連れられて観に行った記憶が残っているのだろう。博覧会が終わった後の7月、日本は満州で盧溝橋事件を起こし8年にも及ぶ戦争へと突入することになる。
第2巻の昭和24年版では、GHQの旗振りで導入された「男女共学」が重要なモチーフのひとつになり、新制高校3年の男女5人が躍動する。当時は作者も高3だから、自らの体験が色濃く反映されているだろう。
その学校の女先生として登場するのが、第1巻にも出てきたお寺の娘。今風でいうとかなりキャラの立った魅力的な「男装の麗人」だ。殺人事件が起きた後、この女先生の声掛けで、やはり第1巻で少年探偵をつとめた看板画家が信州から名古屋へ出てくる、という流れだ。
しかし一方には、戦時から敗戦後の価値観激変についていけない先生や大人たちもたくさんいて、さまざまな葛藤が生じる。戦争の影も色濃い。その空気を生で体験した辻青年の想いが小説の肝になっているとみる。これ以上はネタバレになってしまうので、読んでみてほしい。
■名古屋の街と車窓 文字で蘇る
この2冊でもうひとつぼくに迫ってきたのは、昭和12年と昭和24年の名古屋の街の様子が克明に記されていることだった。広小路通りや大津通りの大きな建物や街並みの様子が、しっかり描かれている。車や電車から眺めるような記述も多い。実在した老舗の料亭や大店なども、おそらくは名前を変えた上で登場している。
第2巻『たかが殺人じゃないか』の主人公である高3生のひとりは「中心街栄町に稀な焼け残りの勝風荘」の御曹司という設定である。時は昭和24年、この老舗料亭は100m道路を作るために立ち退きになる直前という記述も出てくるから、翠芳園がモデルなのだろう。名古屋生まれの人なら、作中のほかの登場舞台もモデルを容易に思い浮かべることができるだろう。
ぼくは生まれも育ちも舞鶴市で、名古屋に出てきたのは昭和46年である。戦後復興についての講演『久屋大通を語ろう』も、当時の写真が最大の頼りだった。残念ながら東京と比べると、名古屋がらみの本や映画は数が少なく、当時の街の様子がCGで再現されるケースもほとんどなかった。
どちらの作品も巻末に3ページにわたって参考文献が載せてある。作者が自分の記憶を補強するためだけでなく、当時をできるたけ忠実に再現し、後のなぞ解きにも備えてディテールを書き込もうとした結果だろう。
生まれ育った町が舞台のフィクションでありいま88歳なのに、これだけ資料を読み込み公開するのかと、ぼくはそこでもプロの気構えを感じた。こんな褒め方をすると、本人やほかの作家の方から「これくらいは当然ですよ。もしかして新聞記事は違うのですか?」といった反応が予想されるけれど…。
■中身評価の3冠 昭和36年版に期待
昨年末に読み始める前は正直いうと、「ミステリー部門3冠」は出版社の話題作りか、88歳レジェンドへの名誉賞ではないかと疑っていた。元新聞記者の一番いやなところが顔をのぞかせていた。読み終えたいま、ミステリーに詳しいわけでもないし、ほかの候補作を読んでもいないのだが、疑いは的外れだったと思う。中身の濃さと面白さがそのまま評価された結果だろう。
2巻の裏帯には「昭和36年を舞台にした続編を構想中」とある。昭和36年といえば東京五輪・新幹線開通の3年前ですでに関連工事が始まっていた。名古屋では御園座が焼失した年でもある。第2巻の高3生のうちだれが再登場し、どんな事件となぞ解きが展開するのだろう―。お楽しみはまだ続く。
【付録】芯ある作家はみな昭和ヒトケタ
ぼくは昭和27年の生まれ。しかも戦時中のことは両親も多くを語らず、中学や高校でもほとんど教えてくれなかった。だから戦前戦後に起きたことは本や映画で少しずつ追体験してきた。その過程で「この人は芯があるなあ」と感じる作家や俳優に「昭和ヒトケタ」が多いことにあるとき気づいた。このサイトに入れた作家や俳優にもたくさんいる。たとえば―。
- 城山三郎 昭和2年8月 『そうか、もう君はいないのか』
- 藤沢周平 昭和2年12月 17作品
- 向田邦子 昭和4年11月 『冬の運動会』
- 半藤一利 昭和5年5月 『昭和史』『日本のいちばん長い日』
- 曽野綾子 昭和6年9月 『人間にとって成熟とは何か』
- 山田洋次 昭和6年9月 関係10作品
- 高倉 健 昭和6年4月 関係10作品
- 五木寛之 昭和7年9月 『新老人の思想』『孤独のすすめ』
昭和7年生まれの辻氏もこのリストに加えたい。ぼくが感じる「芯」はやはり、思春期に戦争を体験していることが大きいのだろう。敗戦を期に価値基準ががらりと変わったこと、それに合わせることができた大人と合わせられなかった大人がいること、それらがもたらす悲喜劇を目撃している。それゆえに戦後日本におきた事件や事故くらいではびくともしない図太さが育まれたのだと思う。