大統領選とデモ 反戦と反知性
昨年の話題作だ。1968年に米シカゴで起きたベトナム反戦デモと警察の衝突、その後の法廷闘争を描いている。ぼくは途中から1月6日にワシントンで起きた連邦議会占拠事件と比べていた。ともに大統領選とデモの組み合わせ。米国民の政治への熱は変わっていないが、52年の時を隔て、熱を噴出するマグマは「反戦」から「反知性」へと変質してしまった。
(アーロン・ソーキン監督・脚本、2020年10月、Netflix配信)
<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます
この映画が描いた1968年は世界的にいわくつきの年で、米国は大統領選があった。現職ジョンソンはベトナム派兵増強に乗り出しており、反対派が反発を強めていた。4月にキング牧師、6月にロバート・ケネディ議員が暗殺され、先進国はどこも騒然としていた。
反戦派は民主党の次期有力候補もベトナム増派路線とみて、党大会にあわせてシカゴに集結し、警官隊との大規模な衝突に発展した。当時の検察は立件を見送ったが、新大統領にニクソンが当選すると新法務長官が反戦リーダーたちを「危険な駄々っ子たち」と呼んで起訴を検察官に命じ、裁判が始まる。反政府活動への見せしめが狙いだった。
■冒頭にエッセンス 検事の発言に注目
観終わってから思ったのは、この映画をきちんと理解するには冒頭の6分を集中して観て、頭に入れることが大事ということだった。この裁判は米国ではとても有名らしい。事件の構図を観客の多くが大体わかっていることが前提になっているだろう。しかしぼくの予備地知識は恥ずかしながら「昨年の話題作」だけ。中盤から終盤にかけての法廷論争やリーダーの路線論議がいまひとつ飲み込めなかった。
この映画はNetflixが独占配給している。視聴者は希望箇所にすぐ戻れる。最後まで見てからすぐに冒頭部分を観直したら、共謀罪での起訴を命じられたシュルツ検事が新法務長官にこんな趣旨の反論をしていた。「その法律は黒人排斥のために作られた」「起訴には値しない」「言論統制の批判を受ける恐れ」。命令をしぶしぶ承諾後も上司に言う。「かれらに格好の舞台と観客を与えます」。法廷は予言通りに進む。この検事も主役だとぼくは思う。
■ベトナム反戦とトランプの反知性
ただ映画の大半は反戦活動側から描かれていく。法廷場面の最後は、被告リーダーが、保守的な裁判長から弁論時間を与えられて”純粋な反戦行為”を展開する。裁判長が制止してもやめず、賛同の輪が広がっていく。その余韻に浸っていると、字幕が裁判後の動向を静かに伝えていく―。
この映画を観ながら思わず連想した連邦議会占拠事件は、まだ生々しい。リベラル志向の目線からだと、トランプ大統領の一連の発言や行動のツケがたまりにたまった「象徴的な末路」だったと、総括して批判するのはたやすい。しかし7400万を超える国民がトランプに投票した事実と、死者まで出たあの騒乱を観た後に支持者の何割かが抱いたであろう失望は重い。
トランプ支持の根っことされる「反知性主義」は、内田樹氏の論評に説得力を感じる。既存の権威や価値やメディアを頭から毛嫌いする、理論的な説明や実証に耳を傾け納得できれば意見を変えるという柔軟性がまったくない、といった志向とぼくは解釈している。
同じ大統領選でも52年前の運動エネルギーは反戦だった。この変質をどう解釈すればいいのだろう。日本の社会や政治でも同じような傾向があるといっていいだろうか。
■実話再現に定評 トランプ版も近い?
アーロン・ソーキン監督はwikipediaによれば、まず先に脚本を書き、曲折を経て監督も担当したようだ。その前にはあの『ソーシャル・ネットワーク』の脚本を担当し、アカデミー賞を獲得していた。フェイスブックがまだ創業から間もない時期に、若き創業者の協力も得られないまま映画にしてしまう度胸と力技にぼくは驚愕した。
今回も実話をもとにしたドキュメンタリータッチの映画だ。『ソーシャル・ネットワーク』のスピード感からすると、この監督かハリウッドのだれかが、トランプ大統領の4年間と最後の連邦議会占拠を題材に、早い時期に映画化すると想像する。リベラル派が多いとされる米国映画人がトランプと反社会主義の内実をどう描くか。
早く観たい。と同時にかなり怖い。というのも、トランプという人物と取り巻きの実態は、ぼくから見て、さまざまな最近の暴露本よりもさらに低俗で醜悪だったと描かれる可能性が高い。そんな映画を観たら、貴重な4年という時間まで費やして残されてしまった「分断という重症」を米国はきちんと治療することができるのかと心配になってしまうに違いないから。
/IMG_65191-scaled-e1602333252669-640x360.jpg)


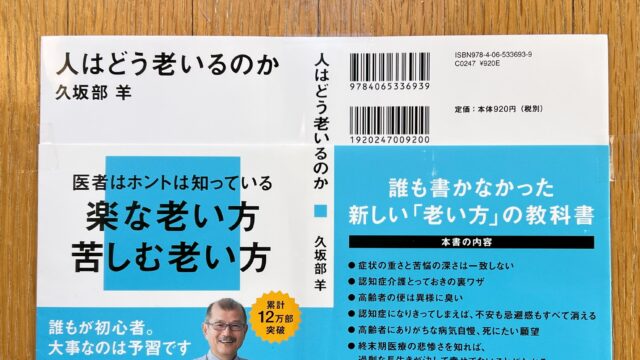
/IMG_7251-scaled-e1602331978805-640x360.jpg)

