同調社会への違和感 一人称単数の目線
(森達也監督、2019年12月公開、イオン長久手)
森達也監督のドキュメンタリーといえば『A』(オウム真理教の荒木浩被告)、『Fake』(「盲目の作曲家」を自称した佐村河内氏)と、かなり特殊な世界において、かつ個性が際立った人物を追いかけてきた。
その次がなんと、望月衣塑子記者である。前作の対象ふたりは「社会的には葬り去られた人たち」だろう。しかし望月記者は、官邸の官房長官会見で沖縄・辺野古の埋め立て問題を含む安倍政権が嫌がる問題についてへこたれずに質問をくりかえしている。そんな記者活動をまとめた本もある。
いわば「異端だが、それゆえに目立つ社会部記者」である。どちらかといえばプラス評価いっぱいの女性だと思われるため、ドキュメントの対象としては前2作とは真逆だろう。とはいっても、恥ずかしながら前の2作を観ていないので、この比較は正直、自信はない。
このドキュメンタリーの本質はやはり、タイトルの「i」にあると感じた。森監督の最初の言葉にある「一人称単数」だ。「不特定多数」「同調」「空気」「予定調和」を優先しがちだとぼくも思う日本社会について、監督は違和感や危機感を強く抱いていて、それを望月記者の奮闘を通じて伝えようとしている。
そうした社会に対する監督の目線は、終盤にはさみこまれる「魚の群れ」の映像や、第二次大戦の開放後のパリであったという「ドイツ兵の子を産んだフランス女性への集団リンチの写真」に投影されている。
その違和感はもちろん、官房長官会見で望月記者がしつこく食い下がっても追随してこない他メディアの記者とか、デモ行進で同じスローガンを叫ぶ参加者たちへも向けられている。
ぼくは望月記者と同じ新聞社に所属する元記者だ。不動産事業という、新聞社の中では編集からもっとも遠い職場に移ってすでに10年がたっているため、いまの編集の人たちのとらえ方は想像するしかない。「組織内記者」として34年過ごした個人的感覚からすると、望月記者の奮闘ぶりは称賛したい。もっといえば、うらやましく、まぶしくもある。
その一方で、記者を離れた立場からはほかに思うことも多い。ひとりの記者の取材過程をドキュメンタリーのカメラがはりつく形で映画作品になることについて、組織ジャーナリスト集団としてどんな議論があったうえで、どういう目的とスタンスで協力したのだろうか―。ぼくの職場までは伝わってはこなかった。
ぼくがもしずっと編集局にいて、このドキュメンタリー取材にかかわる立場にいたとしたら、機微な問題や論点が多数浮かんできて、即取材OKとか全面協力の決断をできただろうか。正直いって、自信がない。
ぼくの新聞社には、一見すると一定方向の論調で固まっているように見えても、個人的にはかなり温度差があり、異論を抱える人もたくさんいると思う。さらに、社説が掲げる論調とは異なる考えの記者がいても、強制的に排除したりせずに包含できる「懐の深いメディア」だと思ってきた。今回のドキュメンタリーはその特質がにじみ出たのだろうと解釈している。
イオンモール長久手で午後9時45分から観た。客は男4人しかいなかった。

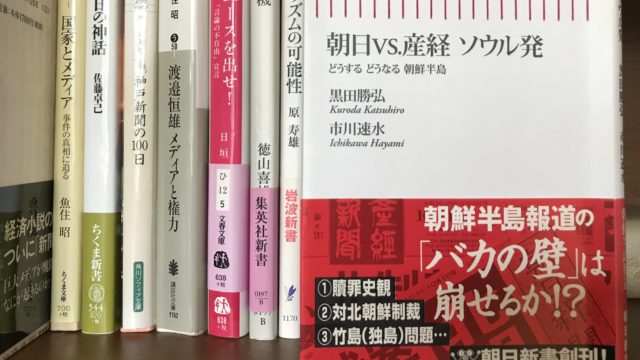


/IMG_6869-scaled-e1602332921115-640x360.jpg)
/IMG_7269-scaled-e1603003962398-640x360.jpg)
