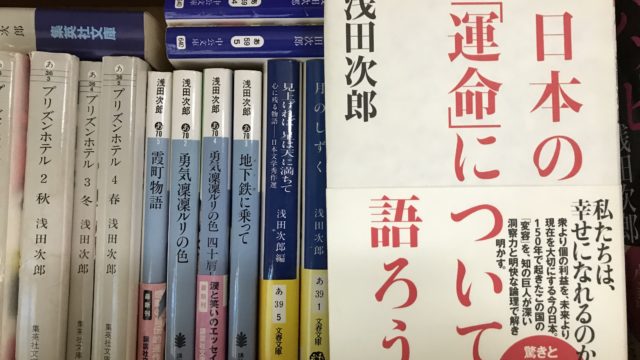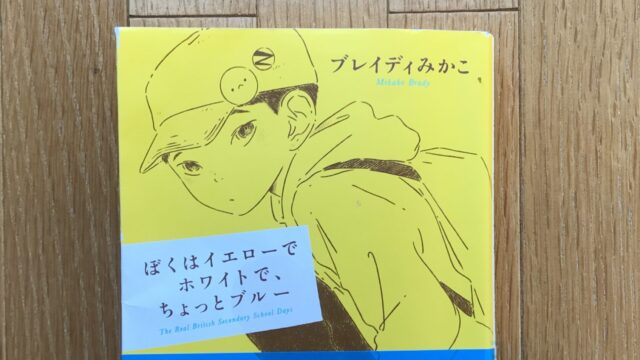(名古屋大学建築学科50年記念誌)
(注) 母校である名古屋大学の建築学科から2013年の秋、学科創設50年の記念誌を出すので「近況報告」の欄に寄稿してほしい、と依頼されて書いた文章です。

かなり異色の選択だったろう。僕は昭和53年春に修士を終えたとき、就職先として地元の新聞社を選んだ。それも技術職や営繕ではなく、記者として入社した。あれから30年、もちろん曲折はあったが、建築からははるかに遠い新聞人の道を歩んできた。しかし人生はわからない。還暦前になって僕は社命で建築の世界に戻ってきた。それも「施主側」という立場で。
なぜ記者に? 新聞社に入ってこの質問を何回うけたろうか。私はこう答えてきた。
「設計が第一志望でした。でもどこも採用してくれなかった。院での専攻は建築史で、図面より文章のほうがうまいかもしれないという自負もあって新聞社も受けてみたら、なんと、合格してしまった。最初はいろんな取材を経験し、いずれは建築・都市の専門記者になりたい」。
やってみると記者は面白かった。富山支局の五年で基礎を覚えた。経済部に十年いてトヨタ自動車や欧米取材も経験した。社会部には七年いて阪神大震災はデスクとして被災地に入った。さまざまな事件を仲間と追いかけ紙面をつくる。朝刊が終わっても未明まで酒場で議論して、夕刊のためにまた街に飛び出していく。そんな記者稼業がどんどん楽しくなった。私の中で「建築」は、記者としてはどうしてもこだわりたい世界ではなくなっていった。
すると新聞人としてもっと広い世界がめぐってきた。特派員としてバンコクに勤務でき、三年間で周辺15か国を飛び回った。編集局次長として北京五輪の現地取材団長もつとめた。
なぜ僕は建築にさほどこだわらなかったのだろう。ふりかえると学生時代の長旅に行き着く。名大で教養のあと一年間休学し、ユーラシア大陸をひとりで貧乏旅行した。小田実の「何でも見てやろう」に触発され、世界の建築と都市をこの目で見て回りたいと欲した。ロシアと欧州全域は鉄道で回った。イスタンブールから中東、アフガニスタンへのシクルロードと、パキスタン・インドはバス。主要な都市では安宿に10日ほど滞在しながら流浪の旅を続けた。
その長い旅は私を圧倒し、自問自答させた。欧州と日本の間には、なんと多彩で多様な文明と歴史と宗教が積み重なっていることか。「地球はひとつ」なんかじゃないぞ。建築は社会を変える力をもっているのか。国のかたちには政治や経済や宗教の方が大事ではないか。そんな疑問を胸に1973年暮れに帰国すると、母国は「オイルショックとトイレットペーパー騒ぎ」に揺れていた。
もうひとつ、僕が建築にこだわらなかった理由はたぶん、復学後の課題設計で見た同窓生の図面だったろう。とても俺にはかなわない。そう思う友が何人かいて、自分の独創性に疑問を抱いた。でも設計意図を文章にしたり、ひとの作品を言葉で評論するのは得手に感じた。
そして因果はめぐる。2008年の北京五輪で取材団長を終えてからしばらくして経営トップに呼ばれた。「キミ、大学は建築だったよね? 社有不動産の活用をやってくれ」。新聞社はネット普及と紙離れのダブルパンチで部数・広告とも伸び悩んでいる。経営下支えのための新設ポストだった。僕らしい「社内転職」である。社員寮や工場の跡地、老朽化した賃貸ビル。それらの活用策を設計事務所やゼネコンの建築出身者らと相談しながらまとめる日々がこの3年、続いている。
こうして「建築」はブーメランのように僕の手のひらに戻ってきた。どうやら神様が「落とし前をつけろ」といっているらしい。とはいっても、いま61歳である。何かをするのに遅すぎると思えば「もう」だろうが、僕はこれからなので「まだ」と思いたい。建築小僧だった学生時代の純真さも、幸い、手つかずのまま「まだ」残っている。(10回卒、S53修士)