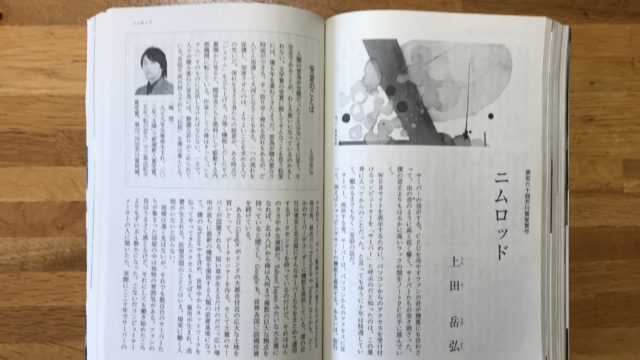定年後のもがきを活写 いずれぼくにも
(講談社、2015年9月)
著者は、テレビドラマの脚本や横綱審議会委員の言動を通して著名だけれど、小説を読むのは初めてだ。妻が先に買ってきて、後でぼくも読んだ。

主人公は岩手県出身の東大法学部卒で、大手銀行で役員手前までいったところで子会社に転籍になり、63歳で退職する。
問題はそこからだ。主人公は経歴やプライドが邪魔になって「定年後の居場所」を見つけられずにもがいていく。スポーツジムに行っても同年代の「ジジババ」の言動に、あんなやつらと一緒にされてたまるか、となじめない。
ジムで知り合ったIT企業社長に誘われて顧問になれたので、やっと居場所が見つかったと思ったら甘くはない。急死した社長の後任を引き受けた後にトラブルに巻き込まれ9000万円の借金を肩代わりせざるをえなくなる―。
定年で「終わった人」になっているのに、それを受け入れられない男が、あれやこれやとのたうちまわる。その姿はあわれでさえある。
筆者はテレビドラマ脚本で実績をあげてきた。場面描写は具体的で目に浮かべやすいし、時にはこっけいだ。交わされる会話は直截で辛口も多い。そこまで漫画的に描くかよという反発を感じた場面もある。
ぼくがいちばんリアルに感じた人物は、主人公の妻だった。筆者は60代後半の女性なので、主人公の男についてはどこかアタマと想像で書いている気がする。しかし妻については等身大で書けているのではないか。
ぼくも63歳、主人公とまったく同じ年だ。まだ現役で大事な仕事をまかされているので「終わった」感はない。だからこの主人公ののたうちまわりは、気持ちは十分に想像できるけど、どこか他人事でもある。
でもあと数年もすれば、ぼくにも「終わる」日が必ずくるのだ。