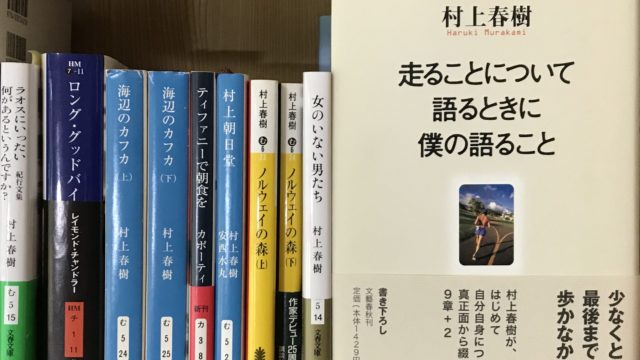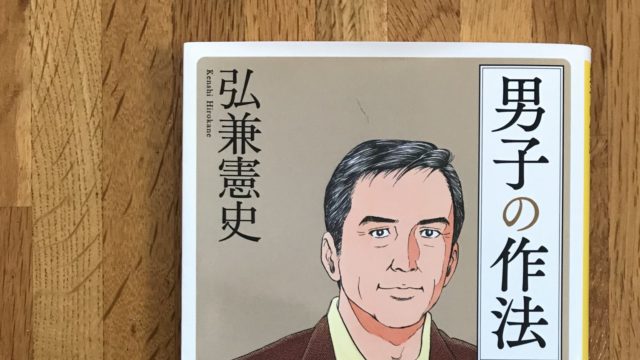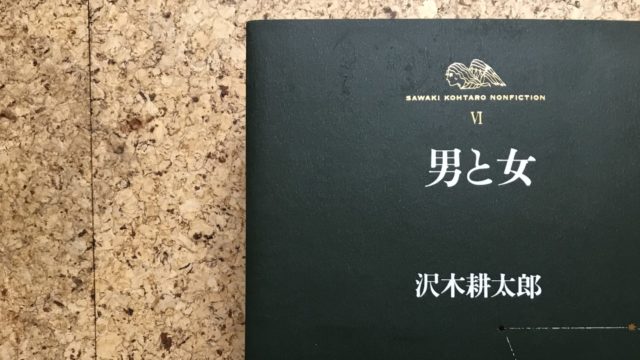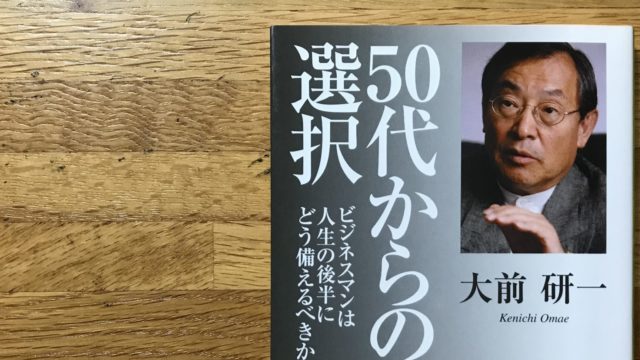小難しい単語はひとつもないのに
(文春文庫、2018年4月)
この作家のエッセイはだいたい読んできた。しかもぼくはバンコクに3年駐在し、ラオスは隣国で取材で2度訪ねたことがある大好きな国だ。このタイトルを見て、すぐ飛びついたのは言うまでもない。

といっても収められているのは、1995年から2016年までの間に作家が重ねた9つの都市への旅の紀行文だった。ラオスへの旅はそのひとつにすぎず、ラオス編の題名も「大いなるメコン川の畔で」。なのに紀行文集のタイトルには「いったい何があるというんですか?」とつけるところが、実に、にくい。この作家らしい、のだ。
ぼくより年が3歳つだけ上の、この走る超人気作家は、小説でもエッセイでも大きな特徴を持っている。そのすべてがこの文集に含まれている。
まず何より、文章が平明だ。そのうえで、文章が含む意味に過不足がない。形容詞の選択は、膨大と思われるストックから見事にそれしかないひとつを抽出してくる。たとえ話も多用するが、そこに破たんがない。えっ、これってどういう意味? という疑問が生じることがないのだ。
食べることや酒を飲むこと、音楽を聴くことに強い関心とこだわりを持ち続けている。
さらには走ることを生活や生きることの一部にしている。ぼくにとってのゴルフに近い。この運動習慣からもきていると思いたい健全さ、ストイックさ、個の目線の確かさ、身体機能への自信みたいなものも文章に強くにじみ出ている。
もちろん軽いエッセイなので、ジョークやはみだしもままある。しかしいずれも村上流の中におさまっていて、外へはみ出すことはない。一定したリズムや質、流れは小説と同じだ。
さて、タイトルにある疑問への答えだが、あとがきにこうある。
「そう訊かれて、僕も一瞬返答に窮しました。でも実際に行ってみると、ラオスにはラオスにしかないものがあります。当たり前のことですね。旅行とはそういうものです。そこに何があるか前もってわかっていたら、誰もわざわざ手間暇かけて旅行になんて出ません。何度か行ったことのある場所だって、行くたびに『へえ、こんなものがあったんだ ! 』という驚きが必ずあります。それが旅行というものです」
この文章には、この問いがどういうものだったのかということと、この紀行文集全体のタイトルにこの問いをもってきた理由が過不足なく説明されている。小難しい単語はひとつもない。さすがだ。