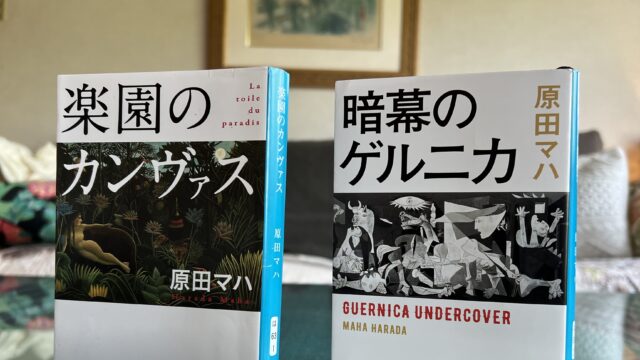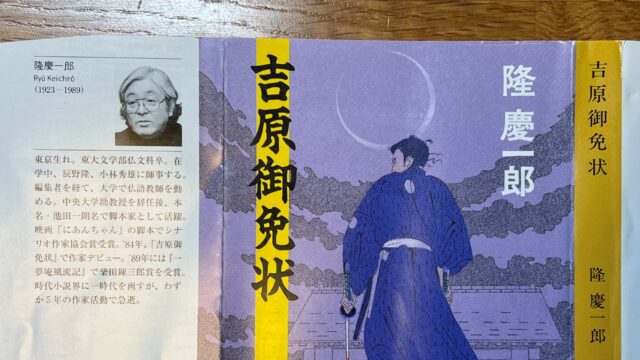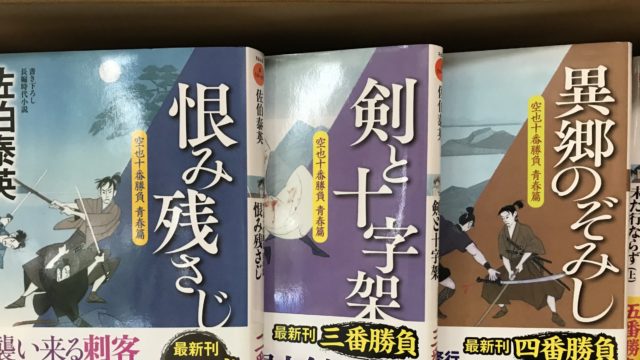老いの孤独 東北弁に乗って突き抜ける
(河出文庫、初刊は2017年11月)
なんと表現していいかわからないでいる。初めて体験する言語空間だった。70代半ばの桃子さんの頭の中に湧き上がるさまざまな思いが、東北弁に乗ってぼくの中に入り込んできた。読み終えた後に湧いてくるこの突き抜け感は何なのだろう。

主人公の桃子さんは、70代半ばの独り住まいである。最愛の夫を15年前に突然亡くし、長男や長女とは関係はよくない。いま日本で急増している独居老人である。しかもなにか事件が起きるわけでもない。
しかし小説の中では、観たこともない世界が広がっていた。桃子さんの若き日の回想やら、夫との出会いと突然死の哀しさやら、その後の孤独な生活に忍び寄るさみしさやらが、不思議な形でこだましていくのだ。
文中に挟み込む形で使われている東北弁が最大の肝だろう。桃子さんの生の気持ちの手触り感とか、心の襞を読者に伝えるのに、これにまさる道具はない。
ただ、そこに表出される桃子さんの思いは単純ではない。あっちへ飛び、こっちへ飛びしていく。ぼくには意味をとりにくい東北弁が何か所もあった。きれいなハーモニーにはなってはいないように感じる。
だがそれらはまったく気にならない。筆者は意図的にハーモニーを避け、生身の人間の老い様を示しているのかもしれない。言葉のすべてが混ざり合い、老いの孤独の向こう側へ突き抜けていく感じがある。いろんな記憶を抱えながら、ひとりで生きていく強い覚悟と勇気を感じさせてくれる。
ぼくもあと2年で70歳になる。このブログで本や映画の感想を綴っていても、同じような心のささやきを感じることがあった。ぼくより少し上の団塊の世代の人たちも同じ感覚なのではないだろうか。映画化という話題だけでは60万部をこえるヒットにはならないと思う。
この作家の経歴も驚きだ。ぼくよりふたつ下で、岩手県遠野市の生まれ。55歳で夫に先立たれた後、息子に勧められて小説講座に通い始めた。若いころから作家になるのが夢だったのだという。
そこまではよくある話だが、63歳でのデビュー作品がこの小説で、いきなり文藝賞と芥川賞に輝いている。当時の新聞でこの人の紹介記事を読み、ふつうのおばさん風の写真を見た時、こんな人もいるのだと元気づけられた。
この作品が原作の映画もいま上映中だ。観るかどうか迷っている。小説の多くは桃子さんの独り言だったり、心の中の東北弁である。登場人物も限られ、大きな事件も起きない。どうやって映画化したのだろう。こんどは映画人のプロの術に触れてみたい気もしている。