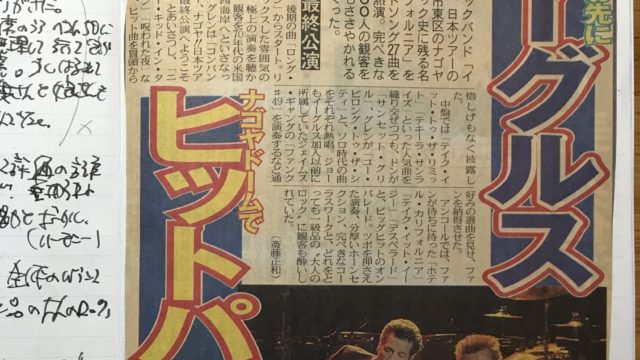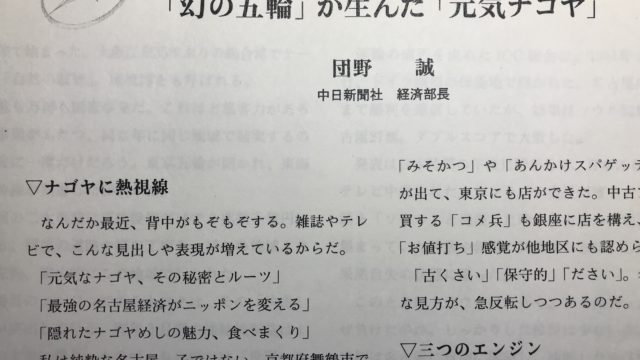風景写真に酒ボトル 地下鉄の駅に「望郷」
(清須市はるひ美術館=愛知県、7月22日→10月3日)
なつかしさや望郷を感じる自然風景の中に「下町のナポレオン」がぽつんと置かれ、詩のようなコピーと「iichiko」のロゴがあるだけ…。地下鉄の駅のホームで見かけるこのポスターが大好きで、毎月の新作が待ち遠しい。過去作品の展覧会を清須市で観たら、駅での掲示は37年も前から続いていて、ひとりのアートディレクターが「ミスマッチ」の魔術を駆使しながら、一貫した姿勢で、制作チームを統括してきたことを知った。

八事駅ホーム 
金山駅ホーム
■37年で450枚 一貫姿勢で統括

ぼくが通勤で使っていた名古屋市営地下鉄でこのポスターに最初に気づいたのは10年ほど前だった。八事駅の鶴舞線ホーム中央部にある掲示板に張ってあった(写真上左)。この展覧会を観てから金山駅のホームでも見つけた(写真上右)。デザインはどちらかというと地味だし、あちこちにあるわけでもない。しかも乗降客はみな急いでいるからポスターに目をやる人は少ない。でもぼくはいつも立ち止まり、ながめるとほっこりできた。
展示資料によると、大分県宇佐市にある酒造会社、三和酒類が「いいちこ」を発売したのは1979年。ポスターの駅掲示が始まったのは5年後の1984(昭和59)年4月、東京の地下鉄からだった。なんとすでに37年もたっている。
月に1回のペースで新作を制作し、地下鉄の駅の決まった場所に1週間だけ掲示するスタイルを続けてきた。掲示する駅も全国へと広げてきた。クリスマス作品もあるので1年に13作、累計で450点以上になる。展覧会には22枚が展示されている。
■河北秀也氏が統括
展覧会の正式な題名は『[ミスマッチストーリィ]河北秀也のiichiko DESIGN』。河北秀也氏はアートディレクターとして、「いいちこ」に関する広告の企画やデザインを1984年から一手に手掛けてきた。

その際に河北氏は三和酒類から「会社は内容には口をはさまない」との約束を取り付けている。それは今日まで守られているという。おそらくコーポレイトアイデンティティの成功例として広告やデザイン業界では有名な話だろう。
ポスターに使われている写真を名古屋出身のカメラマン浅井慎平氏が撮影していることは前から知っていた。会場の展示説明にはこう書いてある。
カメラマンの浅井慎平、コピーライターの野口武、デザイナーの土田康之など特定のメンバーから成るチームによってポスターは製作されています。河北が統括し、写真、コピー、ロゴタイプの配置を含む全体のデザイン、インクや紙質とのバランスを調和させることによって、大人の飲み物を象徴する詩的で瀟洒なイメージが形成されているのです。
つまり河北氏はチームの統括者として、コンセプトからコピー、色使い、レイアウトなど全体を仕切ってきたということだろう。
■「噂で飲まれる酒がある」
1984年の第1号ポスターのコピーはこうだ。
広告の世の中だけど
噂で飲まれる酒がある
ミスマッチストーリィ

この展覧会のコンセプト「ミスマッチ」はここからとられている。ぼくは真ん中の『噂で飲まれる酒がある』にも魅かれる。ポスターにはミスマッチ感や違和感を意図的に残す。それがあるから消費者の記憶に強く長く残り、うわさや口コミを通じて時間をかけてブランド感が熟成されていく、という「ストーリィ」だとみた。
当初作品の写真は自然風景でなかった。第1号はコピーに合わせてオブジェを作り、その写真をあしらっている。その後、海外や離れ島で撮影された自然風景が多くなっていくのだが、良質な後味が長く残るミスマッチ感とか、望郷の念を抱かせる世界観は一貫している。
■駅構内を再現 8つのコーナー

湾曲した展示室に通路と階段と柱を設営
この美術館の展示室は細長くて湾曲している。新しく通路や階段や柱を中央にしつらえることで「地下鉄の構内でポスターを見る」という状況を創出していた。
22の作品は8つのコーナーに分けられている。それぞれにつけられたジャンル名は次の通りで、そのままこの広告ポスターが狙う世界観を言葉で示している。
- 下町のナポレオン、いいちこ
- 春夏秋冬
- 擬態
- 雄大な自然
- 佇まい
- 旅とノスタルジー
- 不在/気配
- 花畑
ポスターはみな「B倍判」というサイズだ。縦が103cm、横が145cmとかなり大きい。写真のどこかに必ず写っている焼酎ボトルは、写真風景と比べると相対的に小さいので、ポスター全体がこれくらい大きくないと「いいちこ」の存在感が伝わらないだろう。
■望郷の念いざなう異郷風景
作品群を観ていくと、ぼくにとつてのシリーズの顔は、日本では目にできない自然や光景の中にさりげなくボトルを置いた作品たちだろう。
2008年11月の『千年のいとなみを思う。』はそのひとつ。パンフによればイタリアで撮影された。草木なき山塊と手前の草地、羊の群れと、それらを見つめるように地上に置かれたボトルが旅情を誘う。
2013年8月の『空想の惑星で。』はニュージーランドで撮影された。海岸の水辺に半円形の黒褐色の岩が並び、手前のいちばん大きな岩の窪みにボトルが置いてある。ネット上のORICON NEWS記事によれば、河北氏のいちばんのお気に入りがこの作品だそうだ。
行ったことも見たこともない異郷だが、見慣れた焼酎ボトルが置いてあることで、ぼくにはこんな風に訴えてくる。
ーー晩酌で「いいちこ」の杯を傾けたら、望郷の念を疑似体験できるよ—ー
■花満開 ふくらむ「酔い」
このシリーズのもうひとつの特長は、花と「いいちこ」の組み合わせだろう。画面いっぱいに広がる花びらたちの片隅に、あるときはど真ん中に、あの「いいちこ」ボトルが映り込んでいる。
1992年1月の『空山独酌』はデンマークで撮影された。ボトルは右の隅、枝の下にひっそりと置かれている。
展示作品でもっとも新しい2019年3月の『帰ってきたと、花。』は八重山諸島で撮影された。花びらの鮮やかな朱色が、真ん中に陣取る「いいちこ」ラベルの黄色と響きあって、春を迎えた祝祭気分と、焼酎から得られるであろう「酔いの愉しみ」を見る者に伝えてくる。
■成熟と郷愁の世界へも
会場作品でぼくがいちばん好きだったのは、2006年11月の『やっぱりここに居たんですね。』だった。

この写真は風景ではない。個人の家の作業場兼納屋だろう。撮影は米マサチューセッツ州とあるから、農家か牧場主の家ではないだろうか。チェーンソーやハンマードリルなどの工具が雑然と置かれていて、棚には雑多な取り換え部品がぶらさげてある。
「いいちこ」はどこにと目を凝らすと、左奥の台の上に置いてある。コピーの『やっぱりここに居たんですね。』からは、日曜大工とお酒が大好きな、カッコイイおじいさんの姿が浮かんでくる。「やっぱり」が効いている。成熟した大人の愉しみと、人生を回顧する郷愁の香りがする。
退職して時間ができたぼくはいま、所属ゴルフクラブの練習場にいる時間が長くなった。このポスターを見ながら、作業場をドライビングレンジのぼくの座席に変え、クラブとボールとマットと芝生と距離表示看板を配した写真構図を夢想したら、にんまりできた。だれかに「やっぱりここに…」と言われてみたい、と。
■「ミスマッチ」の魔術
会場でぼくはまた、展覧会コンセプトの「ミスマッチ」は具体的には何なのだろうとも考えていた。浮かんだのはこんなことだった。どれもあっているかもしれないし、みなピント外れかもしれない。
- 人工物であるボトル ⇔ 自然が作った風景や草花
- 「いいちこ」の庶民性 ⇔ 写真とコピーの洗練度
- ボトルラベルの黄色 ⇔ 風景や花の写真の自然な色
- 生産地は大分県宇佐市 ⇔ ポスター写真は世界の異郷
- B倍判の大型ポスター ⇔ 文字はコピーと「iichico」のみ
- 動き激しいハイテク社会 ⇔ 変わらぬアナログで37年
言い換えると、酒とポスターがもたらすイメージが一直線には重ならない。輻輳しているところが奥深さや余韻を呼び、それが長い時間をかけて良質なブランド形成につながっているように思う。
■『百年の孤独』を後押し?
焼酎ブランドでミスマッチといえば『百年の孤独』を思い浮かべる。もとは南米コロンビアの作家ガルシア・マルケスの代表作品で、この作家は1982年にノーベル賞を受賞した。
宮崎県高鍋町の酒造会社、黒木本店が1985年発売の新商品にこの名をつけ、その意外性と斬新なボトルデザインも相まって人気の”プレミアム焼酎”に育った。ネット情報によれば、社長自らが作家に電話して使用許可を得たという。
当時の常識からすれば、酒の名前に「孤独」はミスマッチ感たっぷりだったろう。しかし黒木本店の社長には、樽の中で3-5年熟成させるという作り方に「孤独」はあっている、本当の酒好きなら孤独は友人になっている、との読みもあったと推測する。
隣の大分県で生産されている「いいちこ」が、東京地下鉄の駅でのポスターでミスマッチ戦略を始めたのは1984年だった。この挑戦が宮崎県の酒造会社の1985年の決断を後押ししたに違いないと、「孤独」が嫌いではない酒飲みのぼくは思いたい。それも見事なミスマッチストーリィではないか。
■五輪バトンと「ミス」マッチ
こんなことをつらつら考えながら展覧会を観た翌日の8月6日(金)の夕食後、「いいちこ」をロックで飲みつつ東京五輪をテレビ観戦した。「いいちこ」を飲むのは久しぶりだった。
もっとも注目していたサッカー男子の3位決定戦があり、日本はメキシコに3-1で敗れた。その後の陸上男子の4×100mリレー決勝ではなんと、1走の多田選手から2走の山県選手にバトンが渡らず、日本チームのレースはおよそ10秒、1/4で終わってしまった。
でも幸いなことに、「いいちこ」の飲み心地は、記憶よりもふくよかで柔らかだった。ポスターから感じる「望郷」や「郷愁」の想いも酔いの中から漂ってきた。
その感覚は、五輪中継で見る海外選手の表情やしぐさの多様性、高校の陸上部時代に走った4×400mリレー第1走者の遠い記憶とも混ざり合った。まろやかな酔いの中で「ミスマッチの奥深さ」を味わうことができたのである。37年前につくられたポスター戦略の魔術、恐るべしだ。