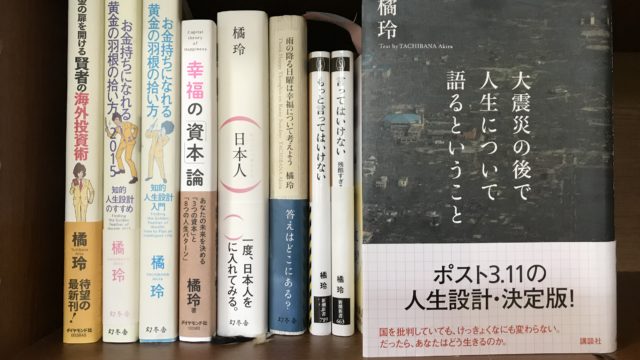選手に沿うA 混乱を抉るB 映画人の意地
(河瀨直美監督、公開はAが6月3日、Bが24日)
東京五輪の公式記録映画『東京2020オリンピック』の「SIDE:A」と「SIDE:B」を27日、連続して観た。コロナ禍で渦巻く開催賛否、1年延期と無観客、組織委会長辞任と続いた異例の五輪を、河瀨直美監督は2部に濃縮した。「A」は選手に寄り添って人生を描き、「B」では運営の大混乱を至近距離から俯瞰しつつ抉っている。「公式の足かせ」を映画人の誇りで越えようとする意地も感じた。でもこの日の観客はわずかで、五輪と映画好きのぼくはまた悲しくなった。

■競技とテーマ 3つの象徴シーン
① 出産後のママ選手…ジェンダー対比
「A」でもっとも印象が残ったのは、出産直後のバスケット選手ふたりだった。
組織委員会はコロナ対策のため家族連れを禁じていた。しかしカナダの選手は3月に生んだ娘の母乳育児を続けるため例外を認めさせた。赤子をあやす夫や母の授乳にカメラは密着する。
日本の予選突破に貢献した女子選手は、1年延期と出産に伴い代表を引退した。仲間が本番で躍動し銀メダルを獲得するのを見て涙する彼女の目を、カメラはやさしくみつめる。
カナダ選手の帰国時に空港で、ふたりのママ選手が愛児をあやしながら語り合うシーンは、全体のテーマ「ジェンダー平等」のわかりやすい象徴になった。
映画のHPによると、3月の会見で河瀨監督は自身も元バスケットボール選手で、高校時代に奈良県代表として国体に出たと明かしている。母でもある。ふたりのママ選手の対比に長尺を割いたのは、河瀨監督の「個」も背景にあっただろう。
② 柔道の男女混合…礼では負けず
もうひとつ「A」で印象に残ったのは柔道だった。
1964年の東京五輪でヘーシンク選手が日本選手を押さえ込みで破って金を決めた瞬間の映像が流れる。ヘーシンク選手は直後に立ち上がり、関係者が畳に上がってくるのを制した。「日本は勝負でも礼でも、2度負けた」と現在の日本コーチが語る。
そして今回、男女混合の決勝で日本はフランスに敗れた。フランスの男女選手は畳の上で輪になって大喜びし審判が困惑していた。字幕も証言もなかったが、この決勝では日本は礼では負けなかった、とのメッセージだとぼくはとらえた。
③ バトン渡らず…ちぐはぐ運営
「B」は、コロナ禍で起きる混乱や組織委のまとまりのなさを、容赦なくとらえていく。1年延期時やスポンサー離れへの対応をめぐる会議の混乱、開閉会式演出監督の交代、そして森喜朗・組織委員会会長の女性蔑視発言による辞任…。

そんな激動を、関係者のすぐ近くから生の表情をアップでおさめた映像を軸にしながら、視線は俯瞰を保っている。反対デモは頻繁に出てくるし、開閉会式チームにいた野村萬斎氏の内部批判や、山口香氏や宮本亜門氏の厳しい意見もきっちりおさめている。
本番の競技でぼくがもっとも鮮明に覚えている場面はBに出てきた。陸上男子400mリレー決勝で、日本の第1走者から第2走者にバトンが渡らなかった。あの痛恨の場面だ。
「個」の実力では劣っても得意のバトンで挽回し再びメダルを取る、はずだった。その得意のバトンが渡らなかった。数えきれないほど練習を重ねたはずなのに…。
五輪の運営も、歓喜の招致決定から7年かけ周到に準備を重ねてきた。日本の「公」のチーム力やおもてなし精神をいかんなく発揮するはずだった。しかしコロナ禍で多くをやり直すことになり、潜在していた弱点やごたごたが一気に露出してしまった。
河瀨監督は、日本得意の「和」や「準備」がコロナ禍開催になり機能しなかったと俯瞰し、その象徴としてバトンミス場面を要所に配したと思う。これも「個」と「公」の相克である。
バッハ会長とIOC
公式記録映画だから画面の冒頭で国際オリンピック委員会(IOC)の名が出てきた。公式HPやパンフには「製作・著作」とある。組織委員会は「企画」の立場だ。IOCは金も出すが、口もしっかりと出せる立場だったと推測する。

だからバッハ会長が何度も登場するのはやむをえない側面もあったろう。フェンシングで五輪に出た時の過去映像や、人生を語る場面ではこれ必要かといぶかったけれど、もっと嫌な感じがしたのが五輪反対デモとニアミスした場面だった。
反対デモに「マイク止め対話を」
バッハ会長がビル玄関で車に乗る込むところだった。近くで「五輪反対」をマイクで叫ぶ集団がいた。会長がそれに気づき「マイクを止め、私と話し合う気はありませんか」と英語で声をかけながら近づいていく。
しかし抗議者はマイクを止めず「反対」を叫び続けたため、会長は「これでは話し合いは無理」と遠ざかっていった。
この場面で会長は本気で話し合う気があったのだろうか。マイクの人は会長の声が聞こえていなかったように見えた。会長には、誘いに乗ってもらえてももらえなくても、こちらから歩み寄った映像は残るという判断があった、とぼくはみてしまった。
バッハ氏の人柄 日本の新旧会長で中和か
フランクで紳士的-。バッハ会長の人柄を思わせる場面はほかにも何度も出てくる。ただその裏側に官僚体質とか貴族意識、IOC利権保護もあると感じてきた。日本の組織委にも同じような不満はあっただろう。
そんな機微は河瀨監督も意識していたはずだ。デモ隊とのニアミス映像だけでなく、バッハ会長が会議でスポンサー問題の対応を「組織委の問題だ」と突っぱねる場面にもそれを感じた。
日本の観客が嫌な感じを受けるのを想定しながらバッハ氏を前に出しつつ、河瀨監督は森喜朗、橋本聖子の新旧会長の個人的回想も何度か挿入することで、バッハ色を”中和”しようとしたとぼくは受け取った。
観客わずか ごたごたに嫌気?
「B」公開後の6月26日、朝日新聞が紹介記事を掲載した。そこにこう書いてあり、断定調にひどく驚いた。
3日公開の「A」は観客が入っていない。
ぼくが27日に訪れた映画館は名古屋市内のシネコン、TOHOシネマズ赤池だった。12時35分からの「A」はぼくと妻のほかは初老の男性ふたり。公開から23日も過ぎているし月曜日だから、こんなものかな…。

ところが午後3時20分からの「B」は、ぼくと50前後の男性のふたりだけだった。封切から4日、ほやほやの新作である。不人気の背景を推測してみる。
- コロナ禍の開催には反対が多く、1年延期の末に無観客となり、組織委にごたごたも続き「負の印象」が定着した
- 「公式記録」なら賛美一色に違いないとの予想
- 無観客だったため感動の度合いが小さく、映像で振り返りたいシーンも少なかった
- コロナ禍は収まらず、2月にはウクライナ危機も始まり、五輪映画どころでない
「A」「B」とも、国立競技場の無人スタンドが何度も挟み込まれていた。映画館でもがらんとした客席をみながら、悲しくてやりきれない気分になった。
NHK虚偽字幕騒動も一因か
もうひとつNHK虚偽字幕騒動も響いただろう。NHKが2021年12月26日にBS1で放映した『河瀨直美が見つめた東京五輪』の中で、河瀨チームのひとりが匿名男性を取材している場面に「五輪反対デモに参加している男性」「実はお金をもらって動員されていると打ち明けた」との字幕をつけた。
抗議を受けNHKは2月10日、不正確な取材に基づく「誤り」だったと認めた。しかしNHKがそんな低水準の誤りを犯すだろうかという素朴な疑問がぼくには残った。五輪反対デモには金で動員された人がいる、それを公式記録映画のチームが取材しようとしていた、と思った人は少なくないのではないか。
河瀨監督は良識ある映画人として、異例の五輪をどう映像に残すか真摯に取り組んできたと信じたい。代表作のひとつ『殯(もがり)の森』を2007年に観た時、ぼくはこう書いた。
国を問わず、人種を問わず、だれにもある心の葛藤を映像に落とし込んだ。
NHK虚偽字幕の番組名には「河瀨直美」が入っているため、河瀨監督が受けたダメージは大きかったと推測する。この騒動が実際の作品への期待をさらにしぼませてしまったのは否定のしようがないだろう。
五輪好きの原点1964 記録映画も
スポーツのテレビ中継で、五輪とサッカーW杯がぼくにとっての横綱で、世界陸上とゴルフマスターズが大関である。記録映画を観るのも大好きだ。
五輪が好きになったきっかけは1964年の東京五輪だった。多感な小6で、開幕直前に自宅にテレビが入った。市川崑監督の記録映画は中学校の授業の一環として映画館で観た。
その後も1968年のグルノーブル冬季大会の映画は、クロード・ルルーシュの映像美と、フランシス・レイの音楽にしびれた。大好きな名作『男と女』のコンビなのである。
新聞記者になると五輪は重要な報道対象になった。1996年アトランタ五輪では事前取材で、2008年北京五輪では取材団長として現地に滞在した。
それらを振り返ると、国家や外交やテロが顔を出す瞬間もあったが、アスリートが繰り広げるドラマと大歓声と祝祭感に彩られていた。
しかしコロナ禍の東京2020は、そんな魅力を根こそぎ奪った。その記録映画を作る難しさは、観て記事を書いてきただけのぼくには想像すらできない。
5000時間を4時間に 映画人の意地も
河瀨監督は1年延期になったため5000時間にも膨らんだ映像記録を、「A」と「B」の計4時間に濃縮した。
五輪では選手や関係者の「個」よりも、かれらが属する国家や民族、組織や会社の「公」が大きな位置を占めやすい。コロナ禍が地球上を覆う中での開催になった今回はさらに「公」が大きくなった。
河瀨監督は選手や関係者の顔のアップ映像を徹底的に多用した。特に目の動きに焦点を当てた。眼は「個」が出やすい。周りを囲む「公」の中で、個人がどう思いどう発言しどんな結果になったか—。
あるいは、五輪とは直接、縁がない自然の俯瞰的な映像を随所に取り入れもした。空と雲、木立と風、水と波…。『殯(もがり)の森』で登場人物の心象風景を表現するときに多用した手法だ。
ぼくの目では、「公」と「個」の相克が全体のテーマだった。予想外の形の開催で途方もない重圧だったと思われるけれど、河瀨監督は公式記録映画として鑑賞に耐える作品に仕上げて「公」に応えた。ぼくはそれ以上に、監督自身の「個」も作品に織り込んで映画人の意地を見せたことをより評価したい。
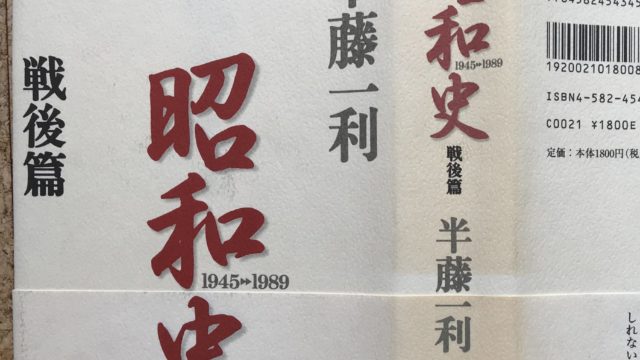
/IMG_7271-scaled-e1602932013768-640x360.jpg)
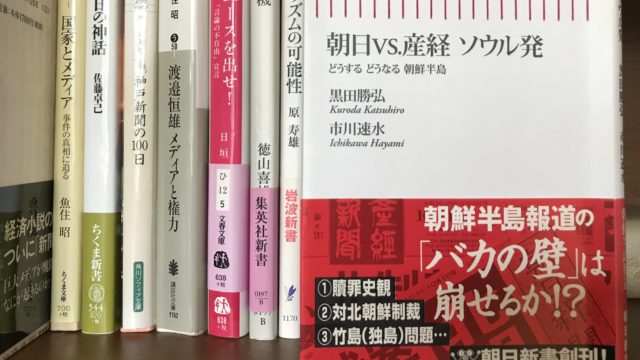
/IMG_7259-640x360.jpg)