原作読み10年ぶり再見 やっと全容理解
(ロン・ハワード監督、公開2006年5月)
10年ぶりにあらためてDVDで観た。直前に原作のケン・ブラウン『ダ・ビンチ・コード』を初めて読んでいたので、今度は中身もよくわかった。うまく映画化しているなあと驚いた。

原作の小説はディテールが詰まっていて、うん蓄は半端ない。説明や描写もていねいで長い。そのぶん大きな筋や人間関係は見えにくくなっている。
映画では、小説的、文字的な説明を極力縮めている。なぞ解きにいたる過程もかなり短くしている。
トム・ハンクス演じるラングストン教授らが、残された暗号の指示を追って行動し、舞台が欧州内で転々と変わっていく。そのあたりは、このミステリーの大きな魅力のひとつであり、映像を駆使できる映画に有利に働いている。
最初のパリ(ループル美術館と鍵)から始まり、スイス(銀行の貸金庫)→パリ郊外(導師の館)→ロンドン(神殿と寺院とニュートンの墓)→パリ(ルーブル・ピラミッド)へと「帰還」していく。
1月9日付け日経新聞「文化往来」欄によると、洋の東西を問わず英雄物語には「出立→イニシエーション(通過儀礼)→帰還」という共通の構造がある、と神話学の古典『千の顔を持つ英雄』が指摘している。『ダ・ビンチ・コード』を読み解くカギにもなるという。この映画を観て、なるほどと思った。
トム・ハンクスは知的で、感情や表情の抑制も効いている。原作のラングストン教授のイメージに近い。キリストに娘がいてその末裔、という設定のソフィーも悪くない。フランスの刑事もすごくいい味が出ている。
残念なのは導師リーか。大事な役どころなのにちょっと軽い。もっと渋みと奥行きがほしかった。フランスの男優で、あの伝説のジャン・ギャバンみたいな人はいなかったのだろうか。
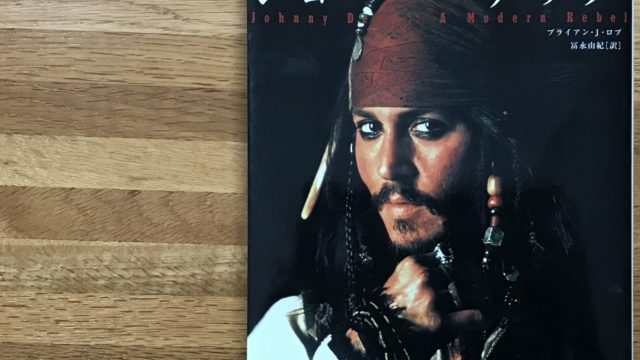
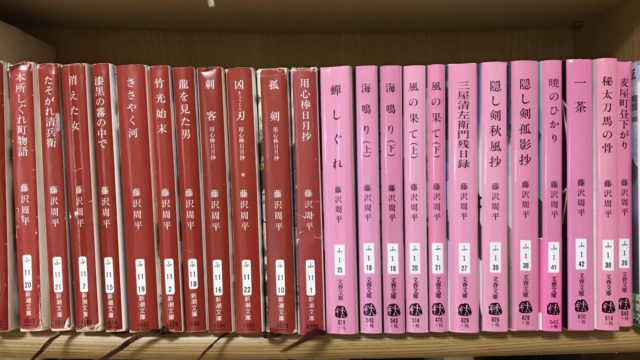
/200910-映画パンフ-scaled-e1602333444977-640x360.jpg)

/IMG_7245-scaled-e1602332136724-640x360.jpg)
