東独監視役が開眼 自由と良心の名作
(フロリアン・H・V・ドナースマスク監督、公開2007年2月)
映画が始まる1984年は、日本では昭和59年、ぼくが初任地の富山から名古屋本社へ異動になったころだ。日本ではバブル経済の助走が始まり、土地・株の狂乱が動き始めていた。
ドイツでは東西の壁の崩壊までまだ5年、というころだ。東ドイツがそのころ、とんでもない監視社会であったということは、壁が崩壊した後の報道で知ってはいたが、この映画を観て初めて実感できた。
市民の生活はそんなに困窮していたわけではなかった。ただ反体制、西欧風の考え方をする人たちへの国家的締めつけは厳しく、特に芸術家たちにはどうしようもなく暮らしにくい社会だったようだ。
主人公は東ドイツ国家保安省の大尉。反体制とおぼしき劇作家と、彼と同棲する女優の徹底的な監視を命じられるところから物語は始まる。大尉が監視を通じ、逆に自らの価値観を変えていく過程が精緻に描かれている。
劇作家は家宅捜索を受けることになるが、「問題作品」の詰まった劇作家のタイプライターは大尉がひそかに持ち出していた。
劇作家は壁が崩壊した後にそれを知り、大尉のコードネームや資料を発掘して「真実」を知る。それをもとに劇作家は、この映画と同じタイトルの手記を出版。この本を手にした元大尉がレジで「これは僕のための本だ」とつぶやくシーンが象徴的だ。
名作だ。ドイツ的良心を感じる。監督は西ドイツ出身の33歳でこれがデビュー作だそうだ。こんなに大きな枠組みの骨太作品を撮れる監督が日本に現れる日はくるだろうか。いや、すでにいるとすれば誰になるだろう。
/IMG_7248-scaled-e1602332055981-640x360.jpg)
/IMG_7254-scaled-e1602331944881-640x360.jpg)
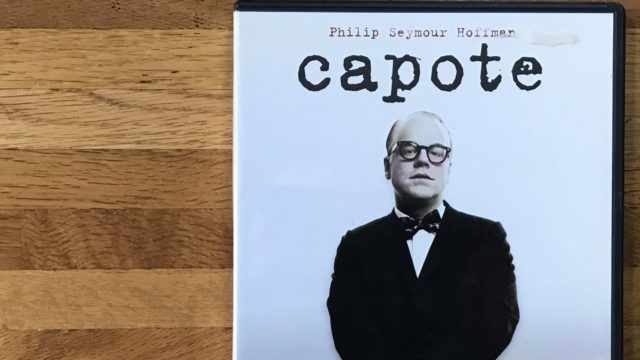
/IMG_7273-scaled-e1602331317429-640x360.jpg)
/IMG_7261-640x360.jpg)

