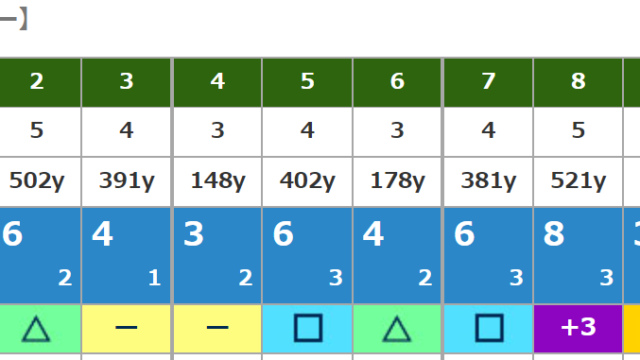米記者の挑戦 君も来いよと強い誘惑
(菅啓次郎訳、朝日新聞社、1994年5月30日)
■きっかけは山口信吾氏
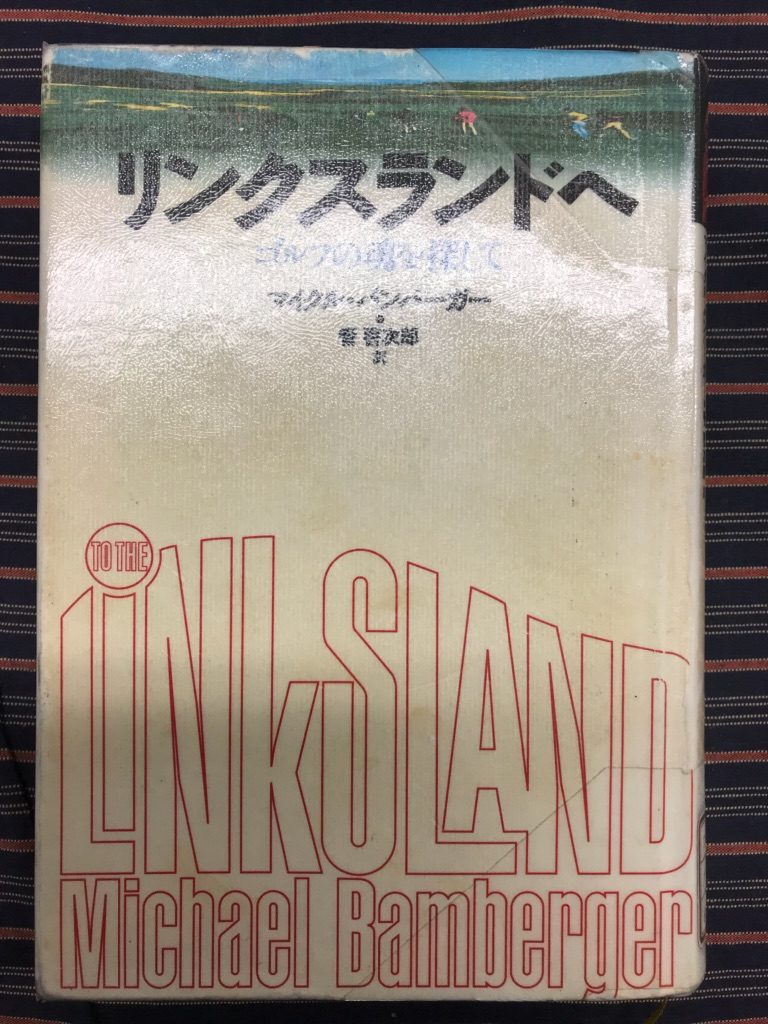
ぼくがリンクスにあこがれるようになったのも、この本の存在を知るきっかけになったのも、もとはみな山口信吾氏である。
2007年ごろ、山口氏の著作『定年後はイギリスでリンクスゴルフを愉しもう』を読んだ。ぼくは当時53歳。念願のシングル入りを果たし、アマチュアゴルファーとして次の目標を探していた時に巡りあってしまった。
山口氏もまだサラリーマンゴルファーだったころに、このマイクル本でリンクスの奥深さを知った。
さらに地元大阪で開かれた日本オープンを見物に行ったら、ピーター・テラヴァイネンが目の前でプレーし、しかも優勝してしまった。そのテラヴァイネンこそ、この本の前半の「アウト」に登場する米国人ゴルファーで、マイクルがキャディをつとめたインテリ・プロだった。山口氏がリンクスに運命を感じたのは当然だろう。
■スウィングを聴け、いい音を生め
ゴルファーの僕としては後半の13章「R・フォーガン」がいい。特に210ページから211ページにかけて、「師匠」スターツが語るスウィング理論にぼくは魅かれる。
きみの問題はすべてテンポについて、タイミングについての問題だ。スウィングの適切なテンポを感じるためには、スウィングを聴かなくてはいけないよ。いいショットをするためには、いいショットにつきものの音を生まなくてはいけないんだ」
シャフトが空気を裂いて生む音を聴き、その音がいかに律動をもち甘やかなものであるかについて、耳をすますんだ。クラブヘッドがボールと、ついでそのすぐ後に地面と、いい接触をして生む音を聴きたまえ。これらこそ、いいゴルフにつきもののすばらしい音であり、それは全英オープンチャンピオンへの拍手のようにすばらしく、ホールへと落ちるパットの音のようにすばらしく、さえずる小鳥たちの歌のようにすばらしい。
このことばを頼りに練習すれば、必ずいい音が出て、しかもスコアがよくなるとはぼくは思わない。律動性と甘やかさをもつ音がどんなものかを説明する言葉も知らない。だが、それを意識すれば、心構えは美しなる。姿勢もよくなるだろう。この僕も、いいショットは必ずいい音を伴っていることは、経験上わかっている。てのひらに残る「芯で打ち抜いた打感」とともに。
■ゴルフ探求か本執筆の取材旅か
著者マイクルは米国の新聞記者である。驚くのは30歳という若さ。ゴルフには青春期から親しみ、一時は70台も出せる腕前にもなったが、そこで止まったとある。野球の大リーグ担当だったが、1年間休職し、しかも新婚の妻と欧州へゴルフ旅に出る。
なんという暴挙かと思うが、本はゴルフ熱を推進力にして前へ前へと進む。前半の「OUT」は欧州ツアーのキャディ体験記、後半の「IN」はスコットランドリンクス修行記である。
読み終えてみるともちろん、ゴルフがもつ奥深さやそれを体現するリンクスコースへの敬意を強く感じる。ゴルファーとしては、うっとりする文体である。だから、断ちがたいゴルフの魅力をもう一度とことん追求し、より高みに達してみたいというマイクルのゴルファー本能はよく伝わる。
その一方で元新聞記者のぼくとしては、こんな読後感も持つ。マイクルは休職の最初から、プロゴルフツアーのキャディ、リンクス体験をもとにしてまとまった本を書こうとしていたのではないだろうか。退職ではなく休職にしたからだ。会う人の選び方やアポの取り方、追跡の方法、聞き出したい言葉への執念からは、ジャーナリストとしての強い目線を感じる。
そのおかげでぼくも、これほど密度の濃いゴルフ論、スウィング論、リンクス論を読むことができるのだが、ジャーナリストとしては軽いひっかかりが残るのも事実だ。
書くことが目的なのを事前に告げずに、ゴルフ修行や会話をするって、本当はどうなのだろう。自分が本物のプレーヤーになりたいという希望を前面に出し、体験を本にしたいという別の目的は奥にしまってはいないか。
ものすごく古いけれど、トヨタの期間工を描いた鎌田慧氏の『自動車絶望工場』をめぐる、ルポ方法論の議論を思い出してしまうのだ。
もしぼくがブログを書き始めれば、同じ悩みに直面するかもしれない。
■翻訳者あとがきもいい音だ
翻訳者の菅啓次郎氏についても触れておきたい。ネット検索によれば、1958年生まれで、愛知県の私立進学高校の出身。東大教養学部フランス科を出て、明大や海外の大学で教える傍ら、さまざまなジャンルの本を書いている。ちなみに同じ高校の作家でぼくの大学の後輩、森博嗣氏は1957年12月生まれだから、森氏が1学年先輩になる。二人はすごく似たにおいがする。交遊があったどうかはわからない。
ウィクペディアによれば、菅氏のゴルフ本は翻訳のこの一冊だけのようにみえる。あとがきによれば、ご自身も、翻訳時の10年ほど前まではかなりのゴルフ熱をお持ちであったらしい。だから、あとがきに出てくるシアトル郊外でのラウンドの様子には、すごく「いい音」が響いている。
1992年の晩夏、ひとりでスタートしようした菅氏に、白いハンチングの地元の中年男が「一緒にいっていい?」と声をかけてきた。途中で菅氏がマイクル本のことを話すと、中年男のデューイ氏は言った。「きみも読んだのか。私も読んだよ」。いいねえ、いいねえ。できすぎぐらいだねえ。
■日米ゴルフ事情への嫌悪感
そんな菅氏のゴルフ熱と翻訳意欲が出た個所が、あとがきにもうひとつある。日米ゴルフ事情への嫌悪感についてだ。書き出してみる。まずはマイクルの嘆きから。これは本にも何度か出でくる。
- ・100ドルもするグリーンフィー
- ・電動カート、雑草ひとつない人工的なコース
- ・5時間も6時間もかかるラウンド
- ・だれもが同じスウィングを目指すアメリカンスタイル
次は菅氏が「いっそう悪い」とする日本のゴルフ事情はこんな点だ。
- 下手すれば数万円もかかるプレー代
- 遠すぎるゴルフ場
- 不必要なままに強いられるキャディ
- 鳥も魚も住めないほど農薬で汚染された土地
- 投機の対象でしかない会員権
- 共同体の精神をまったく欠いた名ばかりカントリークラブ
- 5時間も6時間もかかるラウンド
- 用具の話題にうつつを抜かしディヴォット埋めさえ知らないゴルフ仲間たち
まさにバブル真っ盛り期の日本のゴルフ事情はそんなだった(25年後の今はかなり改善はされていると思う)。こうしたゴルフ環境を踏まえて、菅氏はマイクル本をこう紹介する。
こうした環境で生きながら、ゴルフが出生状態にあったときの純粋な力を求めるためには、ぼくらはある種の犠牲と努力を払って、旅に出なくてはならない。その必要だけはわかっていてもなかなか実行できない。そんな旅を、見事に独力で、生活の危険を賭けてまで実現してくれた、未知の友人がいた。ぼくが感じた快い驚きは、そこにあった。
「未知の友人がいた」に、ゴルフ好きの血を感じる。いいねえ。