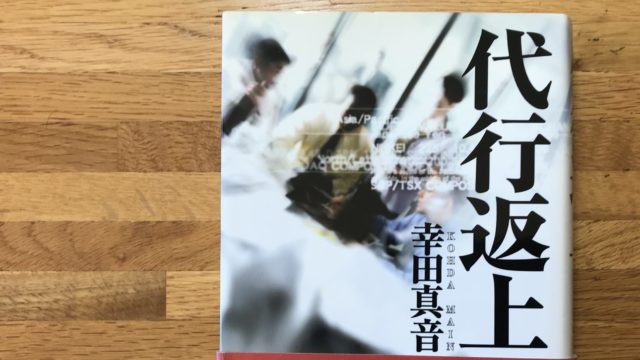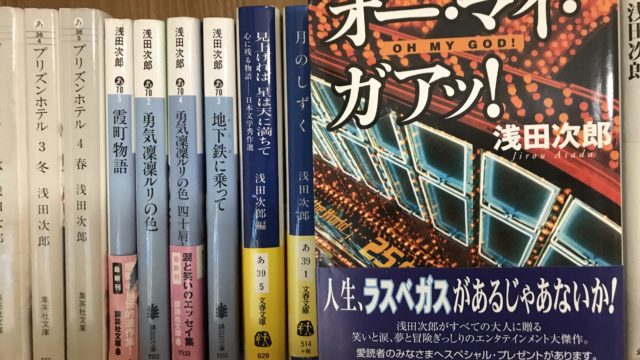老境のこころ洗われ ほんろうもされ
(文春文庫、初刊は1989年)
67歳になった直後の読み直しだったから、深い愉しみを伴った。

筋だけでなく、細かな描写のひとつひとつにまで心が洗われ、時に、ほんろうされる。隠居してからの頼まれごとや、まだ現役奉行である同期との友情をきっかけに、いろいろと駆けずり回る様子は、いまの60歳や定年組にはほぼありえない想定であろう。
主人公が現役の最後に就いていた「用人」というのは、どういう立場なのだろう。社長のそばにいる秘書部長とか総務部長といったバリバリのライン部長ではなく、顧問のような社長へのアドバイス役なのだろうか。江戸時代の藩にはそれこそ、表にはできない「政(まつりごと)」がいろいろあったと時代小説で知るのだが、それが用人にゆだねられるというのは想像しづらい状況ではある。
そんなことより、老境にさしかかった男たちの抵抗とか、終い際の立ち居振る舞いがいろいろ出てきて身につまされる。この主人公のように、大きな心の揺れもなく的確にさばいていける人は、江戸時代も現代もそうはいまい。
清左衛門はやがて、湧中という料理屋をひいきにするようになる。そこに出てくる料理の鮮やかさと、女将との淡い大人の恋模様が切ないほど効いている。残日録というほど枯れた時間ではなく、現役録に近い。
こんな年寄りか隠居でいきたいものだ。