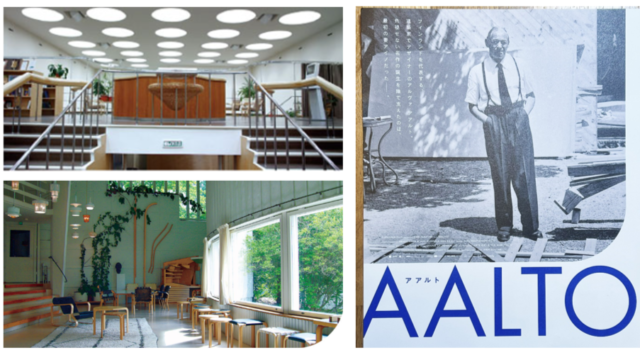(「愛知の建築」2015年10月号)
<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます
(注) 愛知建築士会の外部理事を委嘱されていた2015年に会報「愛知の建築」への寄稿を依頼されて書いた文章。10月号の「論叢」欄に掲載された。
この夏は新写真集『昭和の名古屋』を眺めつつ戦後70年に思いをはせた。昭和21年創刊の夕刊紙、名古屋タイムズの保存写真から、40年代までの約200枚が収められている。焼け野原の栄や名駅がものすごい勢いで変貌していく様子が、とてもまぶしい。
■100M道路とTV塔にまぶしさ

わたしは京都府舞鶴市で生まれ育ち、昭和46年に大学生としてこの街にきた。写真集にはピカピカの外観で出てくる復元名古屋城もテレビ塔も丸栄も大名古屋ビルも中日ビルも、すでにあった。なつかしさよりまぶしさを覚えるのはそのためだろう。
なんと大胆な、とあらためて驚くのが100m道路である。もとは一辺75mほどの街区のつらなり。残ったビルや民家や墓地は移転してもらい、つなげた。造成中の写真は「焼け跡にできた滑走路」のようだ。久屋と若宮の整地がほぼ終わり、その交差点に名タイ本社がぽつんと残っている空撮は象徴的である。
■キーマンは秀吉と寿郎
こんな大胆な復興案がなぜ浮上し実現できたのか。キーマンが2人いた、と勝手に考えている。
ひとりは文句なしに田淵寿郎(じゅろう)だ。戦後すぐ名古屋市長から招かれた内務省技監。100m道路や墓地移転を軸とする「田淵プラン」を驚異の速さでまとめ、21年春には議会を通し実務を始めた。占領政策が24年のドッジラインで金融引き締めに転じた時には、区画整理や換地は立ち止まれない水準まで進んでいた。東京の計画が腰砕けになったのと好対照とされる。
なぜ大胆かつ速くやれたのか。都心が京都のような碁盤状だったのが大きいとみる。その原点をさらにさかのぼると1610年の「清洲越し」にたどりつく。加藤清正らが築城にあわせて南側に碁盤状の城下町をつくった。8万人もの武士や町人が清洲から半年で引っ越したとされる。この町割りが名古屋の骨格になった。大胆で速い復興の隠れたキーマンは清洲越しを命じた家康、というのがわたしの説である。
■大胆ゆえに見失ったものも
といっても、いつの世もなにごとも、速ければよいわけでない。写真集からは、まぶしさとともに「大胆さと速さで見失ったもの」も感じる。
その筆頭は100m道路の生かし方だ。たしかに久屋大通はテレビ塔、地下街と一体になり戦後名古屋のシンボルになった。防災や交通には今後も役立つだろう。だがあの大空間の地上部はその後、なくした街区を上回る価値を都心にもたらしているだろうか。
もうひとつは墓地移転である。区画整理と寺院再建の決め手にはなっただろう。だが墓地は、先人との縁をしのび生きる力をえる場だ。18万もの墓碑が平和公園へ移転したことで、先祖との地縁も都心から離れてしまった。「白い街」と称され、それを市民もなんとなく納得した一因に思えてならない。
やはり爆撃で破壊された旧東独ドレスデンの市民は戦後、がれきをもとへ戻して重厚な街並みを再現したと聞く。石・煉瓦の欧州と木・紙の日本の違いを差し引いても、市民の誇りと姿勢の差は大きい。
こんな意識は市にも専門家にもあるのだろう。『新修名古屋市史』第7巻に大意こんなくだりがある。
「西洋の大通りの機能は軍事・交通から買い物へと発展し都市文化の中心になった。日本では文化的意味が理解されていたとはいいがたい」「名古屋の復興は都市基盤像の平均的な姿を実現した。しかし産業基盤整備と防災が優先され、城下町にあった階級制ある居住地や、公共性ある寺院空間が外された。どんな街にするかのイメージを欠いた都市計画になった」
■8月最後の日曜 久屋のどまつりに希望
どんな街になればと考えつつ8月を過ごしたら、最終日曜日の夜、希望に触れた。久屋公園で観た「どまつり ファイナル」。ふだん閑散としている公園が演舞チーム憧れの舞台に一変、熱気と歓声に包まれた。これぞ都心の広場、雪まつりに負けない―。家康と寿郎が残してくれた遺産を生かしていくのは、あの名古屋っ子らの街への愛着と誇りではないか。その熱を形にする役割を、建築士会の皆さんにも期待したい。