
誕生と変遷 史実と創作 豊潤な謎
雨の日に家でじっくり浸ろう―。その願いがこの梅雨にかなった。まずはアンリ・ルソーの『夢』、次がパブロ・ピカソの『ゲルニカ』。いまも魔力を放ち続ける衝撃作がどう誕生し、いかに数奇な運命をたどったかを描くアートミステリーの連作をついに読んだ。ルソーやピカソが大作と格闘する様と、現代の研究者や収集家の思惑が交互に描かれていく。どこまで史実でどこから創作か。迷宮に翻弄されつつ、名画誕生に潜む謎の豊潤さに酔い、梅雨空のうっとうしさを忘れた。
(新潮文庫、初刊は2012年と16年)
<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます
■『夢』に流れる旋律 放たれる香り
『夢』も『ゲルニカ』も超がつく有名絵画だ。論評はおびただしい数にのぼるだろう。それらを読み込んだ上で作家が作品を文字でどう表現するか。それがまず楽しみだった。
ルソーの『夢』は1910年にパリで描かれ、ニューヨーク近代美術館(MoMA)が保管展示している。『楽園のカンヴァス』では、主人公のキュレーターが1983年に写真撮影に立ち会う場面で、『夢』の絵をこう描写している。

月光に照らし出される密林は、うっそうと熱帯植物が密集している。名も知らぬ異国の花々が咲き乱れ、いまにも落ちそうなほど熟した果実が甘やかな香りを放つ。ひんやりと湿った空気のそこここに、動物たちが潜んでいる。その目は爛々と、小さな宝石のように輝いている。
(『楽園のカンヴァス』84p)
遠く近く、聴こえてくるのは笛の音 ― 黒い肌の異人が奏でる。どこかせつなくなつかしい音色。耳を澄ませば、そのまま彼方へ連れ去られてしまいそうなほど、深く静かな旋律。
月の光に、果実の芳香に、ライオンの視線に、そして異人の笛の音に、いま夢から覚めたのは ― 長い栗色の髪、裸身の女。
彼女が横たわる赤いビロードの長椅子は、夢と現のはざまにたゆたう方舟。夢から覚めてなお、女は夢をみているのだろうか。それともこれは現実なのか。
「甘やかな香り」「ひんやりと湿った空気」「せつなくなつかしい音色」「深く静かな旋律」… これを読み、妻が持っていた『ルソーの絵本』(小学館あーとぶっく)を開くと、ぼくにも”楽園”の香りや旋律を想像することができた。
■『ゲルニカ』の阿鼻叫喚
ピカソは『ゲルニカ』を1937年、パリ万博スペイン館の展示作品としてパリで描いた。残念ながら、この絵の現物を観たことがない。徳島の大塚国際美術館で実物大の陶板模写を観たとき、ぼくは印象を言葉にできなかった。戦争の悲劇がピカソ独特のデフォルメで切り取られていて、文字や文章では説明できないと感じた。
今回の小説『暗幕のゲルニカ』は、ピカソの恋人ドラが初めて『ゲルニカ』の下絵を観たときの印象を、ドラの目線でこう書く。

横長の画面を支配しているのは阿鼻叫喚だった。死んだ子供を抱いて泣き叫ぶ女、人間の男の顔を持った牝牛、折れた剣を握りしめて横たわる兵士。息も絶え絶えにもがき苦しむ馬、逃げ惑う女。いったい何が起こったのか、確かめるように、助けを求めるように、二階の窓から腕を突き出してランプの灯火をかざす人。その家からはめらめらと火の手が上がる。
(『暗幕のゲルニカ』97p)
そして中央には、虚空に向かって高々と突き上げられた拳があった。死ぬ間際の兵士が最後の力を振り絞って突き上げた拳。何ものかに抵抗するかのごとく、命の灯火がまだ消えていないと主張するかのごとく。
「阿鼻叫喚」という語はぼくも浮かんだけれど、肉付けする表現がついてこなかった。筆者は、ピカソの描写を具体的に積み重ねながら観客の目線の裏側ににじみ出る思いを摘み取り、見事に言語表現に置き換えている。このくだりに自信がないと小説にならない。美術館勤務の経験もある作家のキャリアと矜持を感じる。
■当時と現代 つなぐMoMA 介在の資産家
小説の構成はどちらも凝りに凝っている。ふたつの名画が描かれた1900年代前半と、現代とを行ったり来たりするのだ。
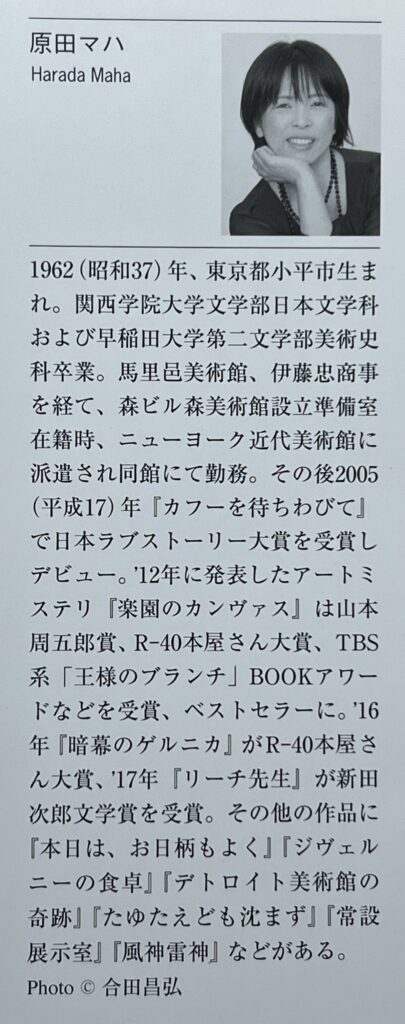
『楽園のカンヴァス』はルソーが1910年に『夢』を描くまでを記録した謎の古書と、1983年のスイス・バーゼルに住む怪物コレクター宅での真贋判定が交錯していく。
『暗幕のゲルニカ』では、ピカソが『ゲルニカ』を描いた1937年からパリ解放までの戦乱の様子が描かれる。そこに2001年「9・11テロ」後の米国の「テロとの戦い」が加わる。さらには、スペインに帰還した『ゲルニカ』をもういちど米国に持ってこようという活動までもが交錯していく。
交錯する時代の橋渡しに大きな役割を担うのがニューヨーク近代美術館(MoMA)だ。著者が作家になる前に勤務した人気の美術館である。ぼくも2005年に訪ねた。
さらにどちらの小説でも、アートに関心を抱く資産家やコレクターが大きな役割を担い、思わぬ展開の主役になっていく。モデルが実在したのか、筆者の想像上の人物か―。頭を巡らせるのも愉しかった。
知的な日本女性も活躍
日本人の女性が活躍するのも共通している。『楽園のカンヴァス』ではパリ大学を首席卒業した伝説のルソー研究者、『暗幕のゲルニカ』ではMoMAのキュレーター。どちらも知的で勝気な撫子である。筆者の経験や理想を投影しているとぼくはみた。
■ダ・ヴィンチ・コードに刺激?
2作を読み終わってから、筆者のアートミステリー創作意欲に火をつけたのは、米国のダン・ブラウンが2003年に書いた小説『ダ・ヴィンチ・コード』ではなかったか、と想像している。2006年にはトムハンクス主役で映画化されて、日本でも大ヒットした。
ぼくは最初に映画『ダ・ヴィンチ・コード』を観たが、わからないことだらけで情けなくなった。キリスト教の知識が乏しすぎた。10年後の2016年に小説を読み、映画もあらためて観直したら、なんとか全体を理解できた気はした。
原田マハ氏の『楽園のカンヴァス』の発売は2012年だ。『暗幕のゲルニカ』が出た2016年には、ぼくもこの2作が気になっていたけれど、大作『ダ・ヴィンチ・コード』を読まないままだったことが心残りで先延ばしにしていた。遅れに遅れ、原田マハ氏の2作を読むのも、最初の発売から10年も後のことし、2023年になってしまった。
つぎは『リボルバー』を
原田氏はほかにもアート小説を何冊も書いているけれど、次に読みたいのは2021年発売の『リボルバー』。ゴッホの自殺の謎がテーマらしい。ルソー、ピカソに次ぐ「巨匠3部作」といえるのだろうか―。
■女性作家 海外もの3人衆
日本でも2000年に入ると、海外の人物や出来事を主題に自在に書いたり、海外に住んで行動する女性が一気に増えてきた。その中でも、今回の原田マハ氏を含めて3人の女性作家をぼくは密かに「海外もの3人衆」と称して応援してきた。略歴や代表作を生年順に並べると―
原田マハ 1962(昭和37)年
総合商社やMoMAの勤務あり/『楽園のカンヴァス』で2012年山本周五郎賞/映画『キネマの神様』の原作も
ブレイディみかこ 1965(昭和40)年
英国在住20年 保育士を経てライターに / 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』が2019年本屋大賞に
ヤマザキマリ 1967(昭和42)年
高校中退しイタリアへ / 2008年から連載の漫画『テルマエ・ロマエ』が話題になり、映画も大ヒット
3人とも、なにごともまだまだ男性優先だった日本を若いころに飛び出て、欧米で暮らしと活動を重ねた。その後、作家や漫画家として独自の作品をしっかりと残している。
生まれ育った年代からすると、いわゆる「均等法第一世代」とまとめたくなる。でもそれは元記者の悪弊だろう。3人とも「個の輝き」は強くて、まぶしい。安易な世代論や男女比較論なんか吹き飛ばすような作品を、これからも発表してくれるに違いない。


/IMG_72731-scaled-e1602932179504-640x360.jpg)
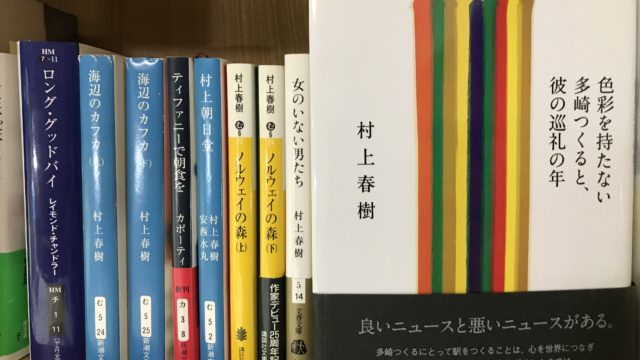

/IMG_7244-scaled-e1602332166584-640x360.jpg)
