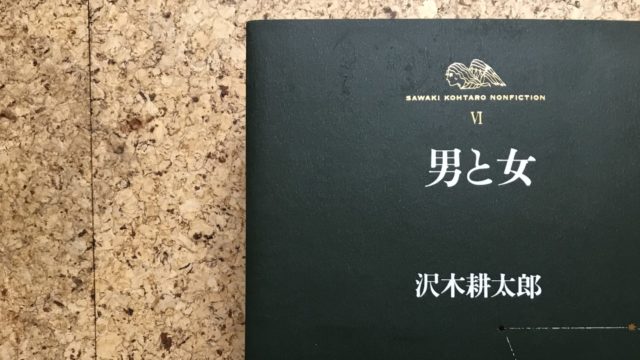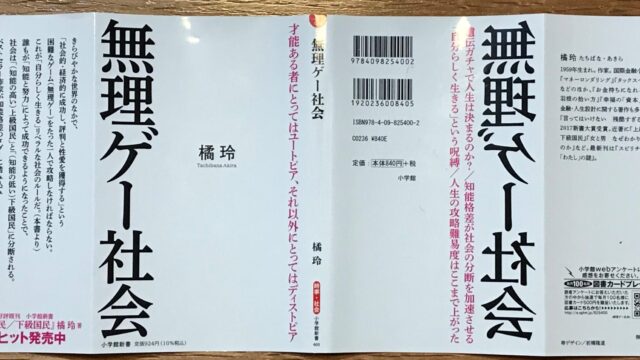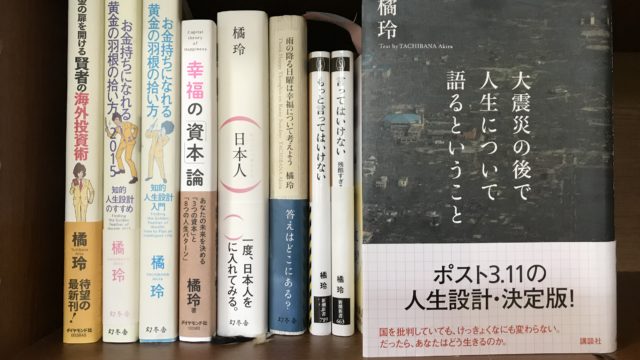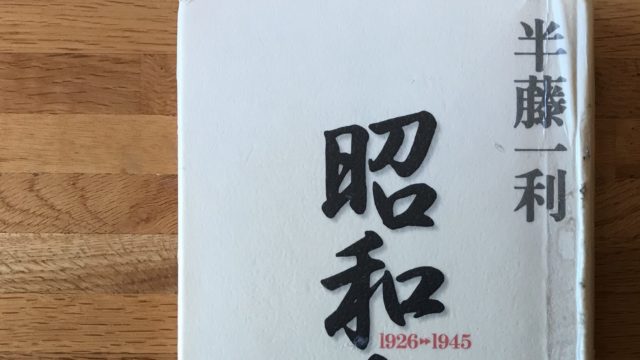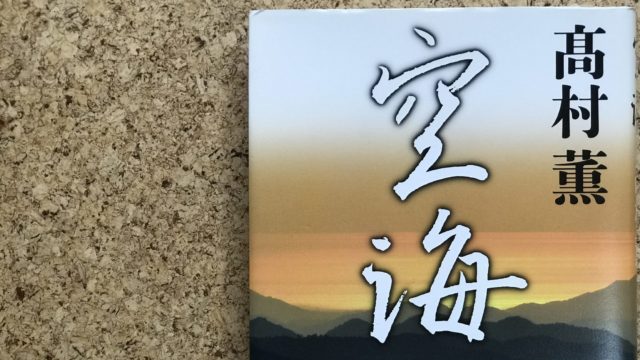「青春の夢 思い出せ」 定年指南の定番に
(中公新書、2017年4月)

サブタイトルが「50歳からの生き方、終わり方」。定年を意識し始めた人たちに向けた「指南書の定番」として、これからも読まれ続けるだろう。
筆者みずからが生保会社に60歳まで勤めた。50歳の時の休業を機に「もの書き」を始め、10年の並走期間を経て定年を迎えている。しかも実際の定年退職者にたくさん会ってロングインタビューも重ねてきている。
だから紹介される実例が多彩である。自分が直接取材した人だけでなく、会社の同僚たち、交流団体で会った人はもちろんのこと、いろんな本で紹介された例、映画やテレビドラマの登場人物も総動員して説明してくれる。
その際も、それぞれの人生に付属しているであろう「余分なディテール」を上手に外して、骨格だけをうまく伝えてくれる。そうすることで、筆者のメッセージを上手に伝えている。文章にくせやよどみもない。
生まれ年は1954年なので、ぼくのふたつ下である。生保のサラリーマンを経て「もの書き」になった振れ幅は、ぼくが新聞記者から定年直前に不動産活用へと社内転職したのと同じくらいか。等身大の人が書いている気がする。
アドバイスの中でいちばん「なるほど」と合点したのは、定年後の居場所ややりたいことを見つけるには、小さいころに好きだったことや、こだわっていたことに再び取り組むように、という部分だった。「子どもの頃の自分と今の自分がつながっていると、それがひとつの物語になる」
ぼくが「小さいころに好きだったこと、やりたかったこと」を振り返ると、小学校ではスポーツ、ギター、新聞記者だった。
スポーツは野球が大好きだったし、走るのも得意だった。野球は社会人になって再開し、いまも社内野球で投げ続けている。35歳で始めたゴルフは死ぬまで高熱は下がらないだろう。スポーツの物語は続いているし続きそうだ。
ギターは下手だけど今も弾いている。人前ではなく、ひとりの時に弾き語りで。これで十分だし、こちらも死ぬまでそっと続けるだろう。
新聞記者はNHKドラマ『事件記者』を観てあこがれ、職業にしてしまった。とはいえ50歳直前から実際に記事を書くことは少なくなっており、こちらの物語を続けるには別の場がいるだろう。これは何か考えなくてはいけない―。
こんな整理をできただけでも、読んでよかったと思う。