
小説と随筆 コロナ梅雨に読む愉悦
山際淳司(1948-1995)は4歳年上の憧れのライターだった。『江夏の21球』を発表した1980年、ぼくは記者になったばかりで、知的で深みあるスポーツ・ノンフィクションがまぶしかった。彼は46歳で急逝したけれど、実は小説やエッセイで「書くゴルフ」を残し、さらに「するゴルフ」も大好きだったと先月になって知った。すぐに3冊を”コロナ梅雨”に読み、ゴルフのもつ魔性と遊戯性をあらためてかみしめた。「読むゴルフ」の愉悦、残してくれてありがとう、山際センパイ―。
<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます
■憧れの人はゴルフも書いていた
6月の梅雨のある日、朝から雨足が強くて練習にも出られないため、自宅で『痛快! ゴルフ学』(2002年、集英社)をながめていた時だった。「推薦ゴルフ図書」のエッセイと小説の欄に山際淳司の名を見つけた。
この人はゴルフも書いていたのか—。ぼくは「読むゴルフ」も求めていたし、筆者は憧れの人もあったから、軽い驚きとともにうれしさもあった。すぐに以下の3冊を名古屋市の鶴舞図書館で借りてきた。
- 小説『ゴルファーは眠れない』(角川書店、1992年3月)
- 随筆1『ダブルボギークラブへようこそ』(マガジンハウス、1994年6月)
- 随筆2『自由と冒険のフェアウェイ』(中央公論社、1995年10月)
筆者は1948年の生まれだから発刊時は44歳から46歳である。出世作『江夏の21球』を書いた1980年から十数年がたっており、スポーツ・ノンフィクションの書き手として円熟味を増しつつあったころと思われる。
■終盤に「カップイン」フレーズ
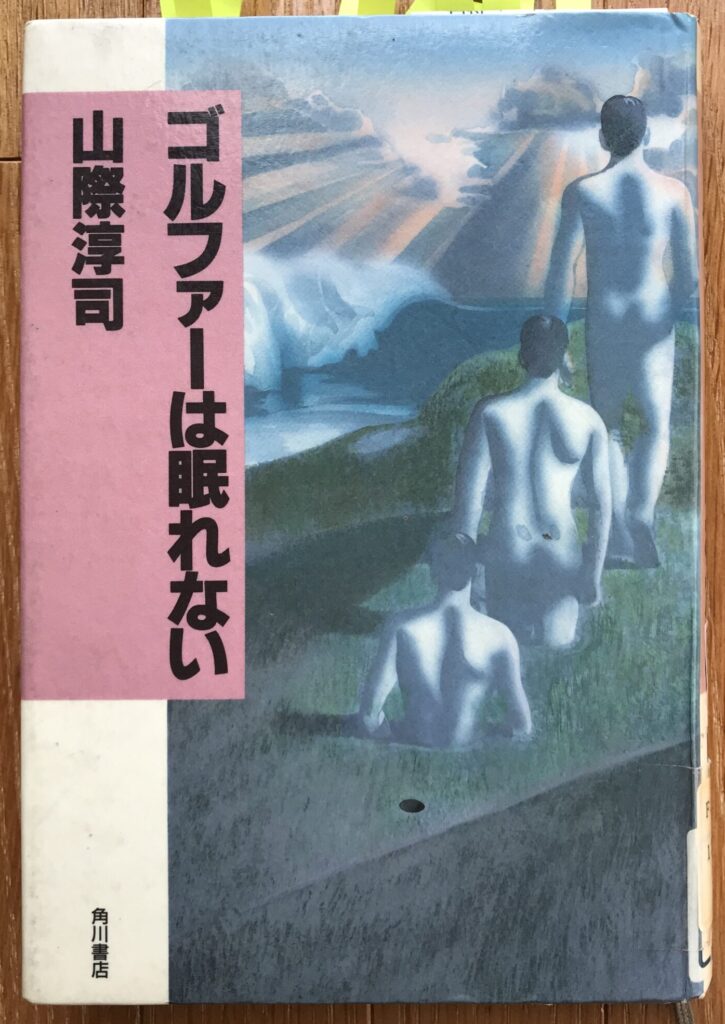
小説『ゴルファーは眠れない』には6つの短編が収められている。海外のゴルフ場も出てくるが、主人公はみな日本人である。終盤に選りすぐりのフレーズがさりげなく出てくる。ぼくにはそれが”カップインの音”に聞こえた。うち5編をおさらいすると―。
- 『オーバー・ザ・レインボー』 ハワイのゴルフ場で勤務しながらプロを目指す若者が主人公。「トワイライトに物思いに沈んではならない」。
- 『ゴルファーは眠れない』 都内のサラリーマン中山は大雨でその日のゴルフが中止になったが、北海道まで飛んでプレー可能に。「この一打を打つために昨夜から眠っていなかったのだ」
- 『葡萄畑にボギーマン』 6週間リフレッシュ休暇の会社員が豪州パース郊外のゴルフ場つき大邸宅に宿泊する。オーナーは「儲けてどうする? 絵を買う? ここには絵以上のものがある」。夜明けと夕暮れの地鳴りは、カンガルーの群れが庭を通り抜けていく音だった。
- 『ゴルフ島奇譚』 パターイップスに苦しむ男は「ゴルフ断ち」の1年がすぎるまであとわずか。ゴルフから逃げるため訪れた島が実は酔狂なゴルフ狂が買い占めた島で、隠れコースが仕込んであった—。「ゴルフは単なる遊びではない。あれもまた官能に訴えるものがある世界なのだな」
- 『北の旅人』 恋人と別れの旅にきた20代女性が、北海道のリゾートコースで傷心のプロゴルファーに初打ちを手ほどきされ「心地よい電流が体を通り抜けていく感じだった」
ぼくは『ゴルフ島奇譚』がいちばん気に入った。ゴルフに取りつかれた男たちの狂気と一途さ、それゆえの哀しさとおかしさが見事に融合されている。島の宿のおかみさんの独白スタイルも「奇譚」らしさを演出していて、どんどん引き込まれていった。こんな島、あるわけないと思うけど、もしかしたら—。
■随筆では「する」「読む」前面に
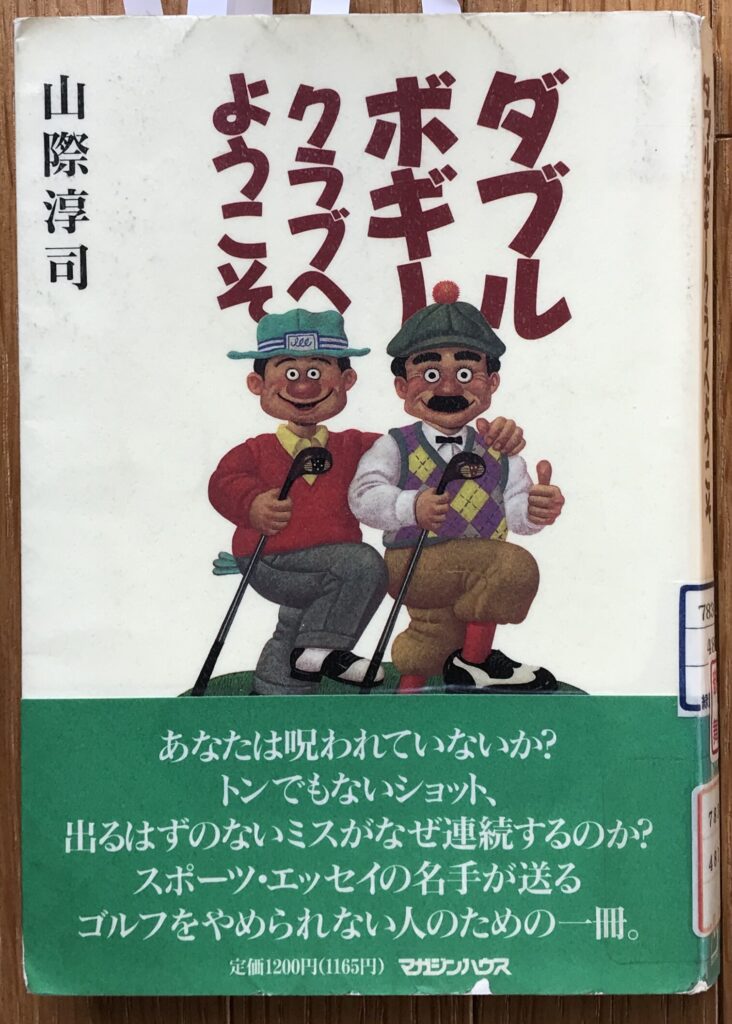
『ダブルボギークラブへようこそ』には23編、『自由と冒険のフェアウェイ』には63編のエッセイが収められている。
どちらも自分のゴルフ体験をベースにした随筆集だ。「ボギーペースの90を基準にしている」とあるから、かなりの頻度でコースに出ていたと思われる。ぼくのように特定クラブの会員にはならず、気のあった仲間とワイワイはやしあいながらいろんなコースを回るのが性にあっていたようだ。
国内でも海外でも取材旅行先で空いた時間があると、宿泊ホテルに近くのゴルフ場を紹介してもらい、クラブを借りてラウンドしていたという。『ダブルボギークラブへようこそ』208ページにこう書いている。
スコアがパッとしないゴルフをしていると、手よりも口が動くというのが大半のゴルファーの性癖で、今日はよくてもダボペースだという展開になると、午後はお喋りの多いラウンドになってしまう。そういうときのために快活に笑えるエピソードをいくつか用意しておくのがダブルボギーゴルファーのエチケットだと思っている。スコアも悲惨で、そのうえむっつりと押し黙ったままフォアサムがアェアウェイを歩いている図はあまりいいものではない。
そういうことをぼくはどちらかというと、アメリカやスコットランドのコースで教わった。
『ダブルボギークラブ』では英米のゴルフ本から得た情報もふんだんに紹介している。かの国にはこんな変なゴルファーがいた、この国ではこんなとんでもないプレーがあった、といった類だ。吹き出しそうな失敗だったり、常軌を逸した短気な男だったりすると、俺だけじゃないんだとほっとするのである。
■急逝前までキャスターとゴルフ
山際は1994年4月にNHK「サンデースポーツ」のメーンキャスターに抜擢されて、いちだんと知名度を増す。故・星野仙一が1985年に初代をつとめた人気番組である。今回読んだエッセイの中に、この仕事を受けることについて「週末のゴルフができなくなってしまった」と書いている。でも冗談半分の調子であった。
それが1995年5月には46歳の若さで病死してしまう。ネットのWikiprdiaによれば死因は「胃がんによる肝不全」とある。
小説『ゴルファーは眠れない』と随筆集『ダブルボギークラブ—』は急逝の数年前であり、みずからに死が訪れる予感などまったくなかったはずだ。
■バブル後の風景 普段着で活写
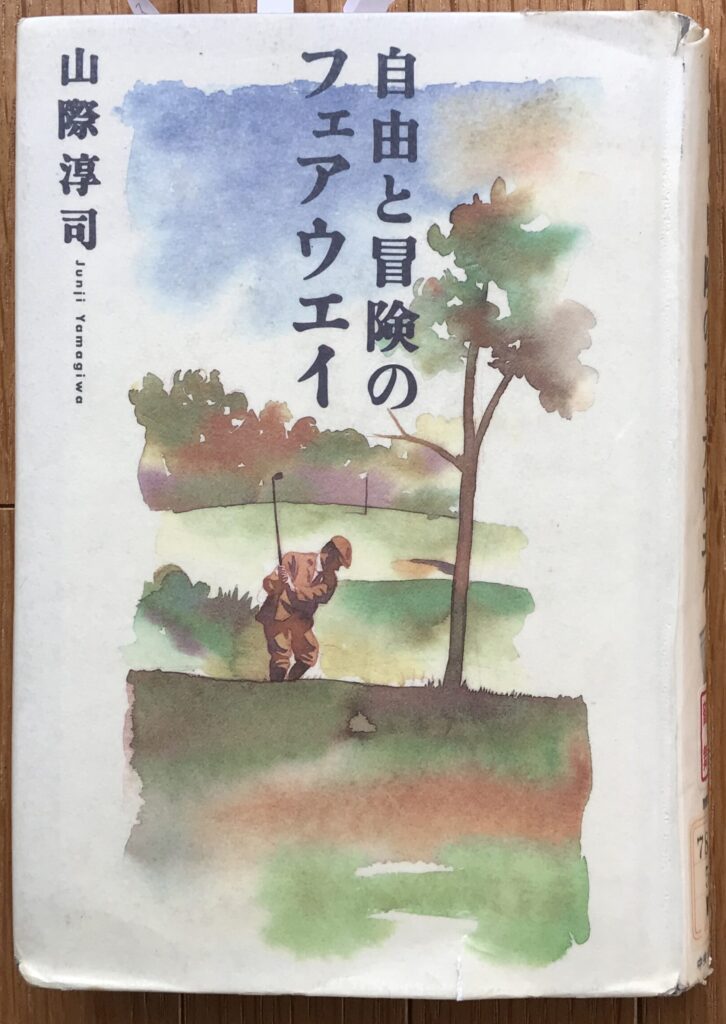
しかし随筆集『自由と冒険のフェアウェイ』は、亡くなる前にいくつかの雑誌に連載していたゴルフエッセイを中央公論社が急遽まとめて発刊したと思われる。『ダブルボギークラブ—』よりも、アベレージゴルファーの目線で、かなり気楽なタッチで書いている。
山際は理性的で知的なライターという印象が強いが、このエッセイでは、自分のプレーについて正直に触れている。頭ではやっちゃいけないと警戒しているのに、イージーミスを重ねたり、無謀な挑戦に出たり、ついキレてしまったり—。「普段着の書くゴルフ」である。
そこには「1990年代前半の東京に住む40代アベレージゴルファー」の気分が満ちている。その前のバブル経済の余韻がまだ強く残る日本のアマゴルファーたちの風景を切り取っている。
ぼくがゴルフを始めたのは1985年秋だった。山際が描いたゴルファー風景は、ああそうだったと実感する場面の連続でもあった。
■「読むゴルフ」の面白さ
『ダブルボギークラブ—』のあとがきによれば、筆者は欧米のゴルフ本を読むのが好きで、小説やエッセイの参考にもした。資料リストの後にこうつけ加えている。
読みだすと、翌日のゴルフに影響してしまうぐらいだ。いずれにせよ、ゴルフを読む面白さを気づかせてくれた先達の仕事ぶりには感謝しなければならない。
これと同じ言葉をぼくは山際さんに捧げなければならない。さらには、これまで読んできた多くのゴルフ本の筆者たちにも—。夏坂健、山口信吾、伊集院静、本宮ひろ志、海老沢泰久、高橋三千綱、中原まこと…。みなさん、ありがとう。
■一緒にフェアウェイを歩きたかった

山際淳司が1980年に書いた出世作『江夏の21球』は、前年11月4日の日本シリーズ最終戦が舞台だ。広島1点リードの9回裏、抑えの江夏豊が近鉄打線に投じた21球をたどっている。近年のプロ野球では中日・巨人10.8決戦と並んで「記憶に残る」試合だろう。
1979年の日本シリーズの時、ぼくは記者2年目で、富山支局のサツ回り(警察担当)だった。江夏の投球はもちろんテレビで観た。山際の『21球』は、翌年のノンフィクション集『スローカーブを、もう一球』(1981年8月、角川書店)に収録された時に初めて読んで、仰天した。
選手たちや監督らの話をもとに冷静な筆と分析力で、交錯する心理模様を描ききっていた。完成度の高さと秀逸なタイトルは、駆け出し記者のぼくにも「書いて伝える」面白さを感じさせてくれた。年も4歳上だけ。さらにひとつ上の沢木耕太郎と並ぶ”憧れのかっこいいライター”になった。
憧れのライターが突然に死去して26年もたってから、ゴルフ本を通じて”再会”できるとは思ってもいなかった。ゴルフを「書く」「読む」だけでなく、「する」人でもあったことがことのほかうれしい。
「書く」ことで残した仕事は足元にも及ばないけれど、ひとりのゴルフ大好き男として一緒にフェアウェイを歩いてみたかった。もしそんな機会があったら、緊張したぼくがパー3のホールで2回続けて手前の池に入れたとしても、次のホールへ向かう道でこうささやいてくれたに違いない。
「ねえねえ団野さん、オーガスタの12番で5打続けてクリークに入れたプロがいたの、知ってますよね ? 」






