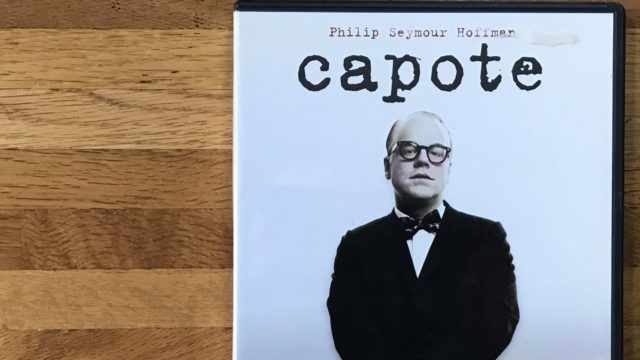百年前の全米OP 覇者は20歳アマ キャディは10歳
いまから1世紀も前、1913年の全米オープンゴルフが舞台だ。コース近くの貧しい家で生まれ育った弱冠20歳のアマが、全英オープンを5度も制していた最強プロをプレーオフで倒して優勝する。しかもキャディは10歳の少年―。この「嘘のような本当の話」は当時の階級差別も批判的に描いていて、ヒーローものを越えた重層感をまとっている。
(ビル・パクストン監督、2005年ディズニー映画、アマゾンで視聴)
<本文の目次> クリックすると そこへ飛びます
■主人公はともに低所得層 差別への闘いも
映画を観るとき冒頭シーンがとても気になる。その作品のエッセンスが詰まっていることが多いからだ。
この映画の冒頭は、1879年の英国ジャージー州、海辺の民家で少年が外の物音で目覚める場面だった。山高帽の男たちがゴルフ場造成の測量をしている。ゴルフって何?と問う少年に山高帽はこう吐き捨てて小銭を放り投げる。「貧乏人に縁はない。紳士のスポーツだ。消えろ」。この少年は後に全英オープンを何度も制することになるハリー・バートン(1870―1937)だった。彼が9歳の時だ。
次の場面は21年後、ちょうど1900年の米国マサチューセッツ州の街。全英3連覇のバートンがイベントで華麗なスイングと打球を披露したあと、飛び入りしてくれる観客を募った。当時7歳のフランシス・ウィメット(1893―1967)が名乗り出て指導を受ける。これをきっかけにウィメットはゴルフにのめり込んでいく。
バードンは当時30歳、ウィメットは7歳。その2人が13年後の全米オープンで激突する。ともに低所得層の出身だけれど、ゴルフの魅力にとりつかれ、才能を磨いていく過程が映画の前半だ。当時のゴルフは貴族や上流階級の男たちだけの世界だったが、ふたりはその差別に立ち向かい風穴を開けていく。
プレーオフ前夜、大会スポンサーでもある英国人の長老はバードンたちを前に、低所得層の子でまだ20歳のウィメットを馬鹿にする。バードンは当時最強のプロで英国人だが、この発言に怒りこう言い放つ。
「我々が闘うのはあなたや英国のためではない。プライドと栄誉のために闘う。もしウィメットが勝てばそれは彼の力量だ。家柄でもない。金でもない。彼自身の勝利だ。当たり前の敬意を払うべきだ」
バードンは映画冒頭で労働者階級の出身だと明かされている。彼の家はゴルフ場造成のために壊された。そうした出自を知っていたから、このセリフにはより説得力があった。
■オーバーラッピングとバードン
ふたりが出会った1900年のイベントシーンにはもっと大きな驚きがあった。バートンは舞台でウィメット少年にクラブを持たせてまず自由に1球打たせた。少年は野球握りで振るがもちろんきちんと当たらない。

次にバードンはウィメットにゴルフ特有の握り方を教える。左手の人差し指と中指に間に、右手小指をかぶせる―。そのシーンが大写しになった。そう、オーバーラッピングだ。そしてこうささやいた。
「ここ(グリップエンド)をね、小鳥だと思ってやさしく握りなさい。でも逃げないように(それなりにしっかりと…)」
ぼくは32歳でゴルフを始めると同時にこの握り方を教則本で知った。「小鳥を両手でつつむように」という活字言葉も覚えている。ウィメット少年がそのグリップでボールを打つとナイスショットとなり観客は拍手喝采する。その時は、100年前からこう握ってきたのかと思っただけだった。
ところが映画を観終わってからネットのwikipediaで「ハリー・バードン」を検索して次の記述に仰天した。「オーバーラッピングを考案したことでも知られ、バードングリップの別名もある」。そうか、だから映画はあの握りを大写しにし「小鳥」の台詞をバードンに言わせたのか、と納得した。
ゴルフにはいま「インターロッキング」という握り方もある。右手小指と左手人差し指をからませる。ウッズや石川遼や松山英樹はこちららしい。ぼくも何度か試してみたけれどしっくりこない。だから今もバードングリップのままだ。こんなところでバードンとつながっていたなんて…。
■10歳キャディ「球にだけ集中を」
もうひとりの主人公が、ウィメットのキャディになるエディ・ロアリー(1902―1984)である。ウッドをぶら下げた長身の20歳ウィメットと、身長ほどもあるバッグを背負った10歳のエディが並んで歩いている写真は「本当かいな」と思ってしまう。ゴルフ史でもっとも有名な画像のひとつらしい。

映画では第2ラウンドの14番ティーにきたとき、ふたりは2位タイ浮上を知る。米国大統領も見物にきていた。ウィメットの緊張が一気に高まり落ち着きを失う。エディは語り掛ける。「ボールだけに集中して」。その後にウィメットのガールフレンドからお守りを預けられるが「女はプレーのじゃまだ」とつぶやきながらポケットにしまい込んでしまう。
第4ラウンドでウィメットがミスをした時はこう声をかけた。「先を考えちゃだめだ。1打ずつ積み重ねるしかない」。それでも動揺が収まらないと、例のお守りをポケットから取り出して渡して気分を変えさせた。「デレデレするな」とリラックスさせることも忘れずに。
最後はプレーオフの18番、1mのウィニングパットの前だった。さすがにウィメットの手が震えていた。エディはささやきかける。「(ラインを)読んで、(しっかり)打って、(そのまま)入れるだけだ」。
日本では4人1組ラウンドだとキャディはひとり。でもぼくはいちどだけ自分専属のキャディさんがついてくれた。2019年秋の所属クラブのシニアチャンピオン決勝戦だった。そのキャディさんは笑みを絶やさず、ミスをすると顔をしかめるぼくに何度も「大丈夫です。今の調子でいけます」と励ましてくれて、最後はいい結果につながった。
コースに出たら頼れるのはキャディだけ。プロやトップアマの厳しい勝負についてよく聞く言葉だ。108年前の米国の大会で10歳の少年の言葉がどこまで響いたのかは想像するしかない。映画のエンドロールで、エディは成人後に事業で成功して大富豪になったとあった。流れをつかみ気分をコントロールする術は生まれつき備わっていたのかもしれない。
■米ゴルフ映画の4部作
この映画はマーク・フロストが書いた伝記小説「The Greatest Game Ever Played」を原作として、ディズニーが2005年に映画化した。マークは原作者というだけでなく、脚本と製作でもかかわっている。これでぼくが観た米国のゴルフ映画は以下の4本になった。
△ティン・カップ (1996年) 原作なし/「一か八か」懲りないプロをコスナーが演じる
△バガー・ヴァンスの伝説 (2000年) プレスフィールド原作/傷心ヒーロー再生と謎の男
△ボビー・ジョーンズ (2004年) 原作なし/「球聖」ジョーンズの葛藤と苦悩
△グレイテスト・ゲーム(2005年) フロスト原作/ 全米OP制した20歳と10歳キャディ
ヒーローとしての魅力なら、やはり『ティン・カップ』の実力俳優ケビン・コスナーが光っていた。ダメさと一途さとをうまく同居させていた。
ゴルフの深遠さなら『バガー・ヴァンスの伝説』がもっとも濃厚だった。原作小説は映画より神秘的な感じがして別世界の気がする。
ひとりのゴルファー物語として観るなら『ボビー・ジョーンズ』だ。4大メジャーをアマとして制した伝説の弁護士である。オーガスタナショナルクラブとマスターズを創設するまでだけでも信じられない成功物語だ。
ゴルフ競技でこんなことが実際にありうるのかという驚きは今回の『グレイテスト・ゲーム』がいちばんだった。最後まで争った最強プロ、ハリー・バードンとの交友、貧しい家に生まれて階級差別と闘う様も重要で、ほかの3作にはない要素だった。
特撮シーンの進化も面白い。『ティン・カップ』では、最後のハイライトシーンは実際のコースにエキストラを入れて実写している。しかし『グレイテスト・ゲーム』になると、球が飛んでいくシーンや大観衆、フェアウェイが回想シーンに切り替わっていく場面にいろんな特撮が利用されている。斬新な映像だったり、漫画的に見えたりといろいろ。いまの最新のCG特撮技術を駆使したらどんなゴルフ映画ができるだろうか。新作の登場を待ちたい。
■来月には2021の全米OP
ことし4月の2021マスターズでの松山英樹優勝の興奮はいまも冷めない。まだ強い余韻が残っているであろう6月17日からは、ことしの全米オープンが開かれる。舞台はカリフォルニア州のトーリーパインズGCである。
松山は2017年大会で2位タイになっている。ことしのマスターズを制したことで注目度は飛躍的に上がるだろう。本命にふさわしい力を発揮できるのか、緊張でプレーを乱してしまうのか。また昼夜逆転でテレビ観戦することになりそうだ。
この映画は108年も前の全米オープンで起きた「嘘のような本当の話」を描いている。英米のゴルフ選手や関係者が、この大会は特別なのでなんとしても勝ちたいという思いをぶちあげる。その思いは当時より強くなっているだろう。そんな価値ある大会で松山には再び堂々とした「横綱」プレーを見せてほしい。
その結果もし幸いにも勝つことができたとしたら、もうひとつ欲深い希望がぼくにはある。最後のセレモニーのスピーチにおいて、全米オープンの長い歴史と伝統について尊敬と感謝の気持ちをきちんと表してほしい。ゆっくりと松山本人の言葉で。1mのパーパットを芯で打ち、ど真ん中からカップに放り込むように。
/IMG_65151-scaled-e1602333370768-640x360.jpg)