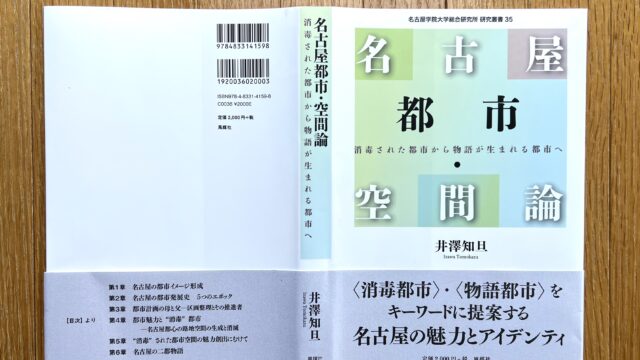にじむ「気構え」 名作たどる愉しみ
(一宮市、2021/1/30~3/14)
ぼくは絵を描くのは不得手だ。しかし一日に何度も自分の顔を鏡で見るので、画家が鏡の自分を見ながらキャンバスに向かえば才能や資質が素直に投影されるだろうことは想像がつく。この企画展は、有名な画家たちの青春時代の自画像からにじみ出る「気構え」を味わい、後年の名作をたどる愉しみを堪能させてくれた。

■58人の作品が時系列に

企画展の会場には日本の画家58人の自画像がひとり1枚ずつ並んでいた。出品リストによると、制作年は1897(明治)年から1966(昭和41)年までと70年もの幅があり、ほぼ年代順に展示されている。
しかし70年という年月差は感じない。画家が自分の顔を描く行為の本質は変わっていないからだろう。
ぼくが「知っている画家」は58人のうち16人だった。「知っている」というのは、その画家の作品を実際に観たことがあるか、教科書か本かポスターで代表作を見たことがあるという意味だ。
■記憶の代表作と共通点探る
まず会場をひと回りした時、どの作品でも目と頭が同じ作業をするのに気づいた。画家の名前を見て「知っている」かまず判断する。知らない画家だと、関心はすぐに次の画家に移ってしまう。

「知っている画家」であれば、記憶にある風景画や人物画と自画像とを頭の中で比べ始める。絵筆のタッチや色づかい、構図に共通点はあるか。あるとすればどこか―。
自画像を単独の作品として観ることがぼくはできなかった。展示作品の大半は、その画家が世に出る前の修業時代に描かれていた。後に評価が高い作品を生んだ表現者は初期作品にすでに萌芽があるという思い込みも理由だろう。
■タッチ・描写力・色づかい
そんな目線で見直してみると、記憶にある代表作と自画像がリンクした画家はこんな人たちだった。カッコ内は自画像を描いた時の年齢だ。
- 黒田 清輝 (31) ベレー帽と口ひげが予想外。でもタッチは『湖畔』
- 青木 繁 (23) 長髪で苦悩する若者の表情。タッチは『海の幸』
- 安井 曽太郎 (25) フランス留学中の作品。セザンヌ風の紺とブルー
- 岸田 劉生 (22) 荒々しく力強いタッチと写実のミックス
- 東郷 青児 (17) 大きな目と鼻と口のキュビズム。「劇画のはしり」
- 佐伯 祐三 (19) 卓越した技量と表現力。「パリの街」の原点すでに
いずれも日本の絵画史に大きな足跡を残した偉大な画家ばかりだ。こんな自画像を描ける力が若い時にあったから後年の名作もあったのか、その後の名作を知っているから若いころの自画像にも訴えるものを感じるのか―。おそらく両面があるのだろう。
■ミスマッチもまた楽し
その一方で、これがこの作家の自画像なのかと、記憶する作品とミスマッチを感じた作品もあった。
- 梅原 龍三郎 (20) 渡欧前、ハンサムで貴公子然。後年のタッチ感じず
- 鬼頭 鍋三郎 (25) 『舞妓』が浮かばない。木炭のデッサンだからか
- 荻須 高徳 (26) 「田舎の模範青年」。パリの香りはまだない
それはそれで面白かった。ぼくの記憶やインスピレーションが的外れかもしれない。作風がその後に劇的に変化していったのかもしれない。それぞれの画家がたどった道は人それぞれで、また別のドラマがあっただろう。
■主役は「20歳の節子」
この企画展の主役はやはり、三岸節子の自画像だった。常設展示場の真正面にその絵はあった。1925(大正14)年、春陽展の初入選作。パンフレットには、このあと70年余に及ぶ画業の原点になった、とある。

しかし作品を実際に間近で見ると意表を衝かれた。うつろな目、弱々しい口元…。当時まだ20歳で、学生結婚して長女を出産した直後だったという。なるほどと、なんとなくわかった気になった。
でもさらに見つめていると、瞳の中に強い自我が燃えているのを感じ始めた。そうすると、羽織の下に着こんだ着物に配した赤色、紺色との格子模様から、画業にかける気構えも伝わってくる。
この絵の存在がこの企画展の起点であり核になっている。集められたのは単なる自画像ではない。「若き日の作品」「三岸節子に影響を与えたり、交流があった画家たち」という観点で絞られた。その狙いはとてもよく伝わってきたし、十二分に楽しむことができた。
■「後の名作」スマホ検索も
この美術館は尾西市(合併後は一宮市)の三岸節子生家跡に1998年にできていた。名古屋から近いのに訪ねたことがなかった。この企画展を知った時から行きたかったが、つい後回しにしているうちに会期もあと10日になっていた。
一宮といえば喫茶店の「モーニングサービス」が有名だ。「近くでモーニングをいただいて、その足で自画像展を観ようよ」と妻を誘い、やっと3月4日に訪れた。
自画像展の会場に入ってしばらくすると、妻は中央ソファに腰かけてスマホを見ていた。見学後に館内カフェでこう話した。「黒田清輝とか青木繁の絵を観たら、その人の有名な作品を思い浮かべたけれど、自信がなくてスマホチェックしてたの」。名作をたどる”連想ゲーム”はぼくと同じ。そうかそんなイマドキ鑑賞法もありうるか、と膝を打った。
会場外に掲示されていた朝日新聞記事に、企画監修にあたった伊藤和彦学芸員の言葉が載っていた。「自画像の魅力でしょうか。普通の絵画展よりも一人ひとりの滞在時間が長いように見えます」
若いころの自画像を見つめながら、その画家が後に描いた代表作を思い浮かべて楽しんでいたのは、ぼくや妻だけではないらしい。