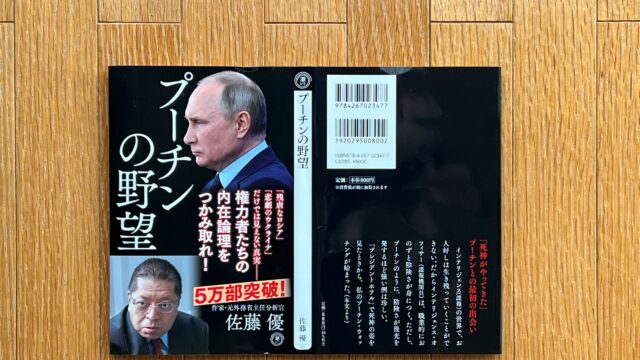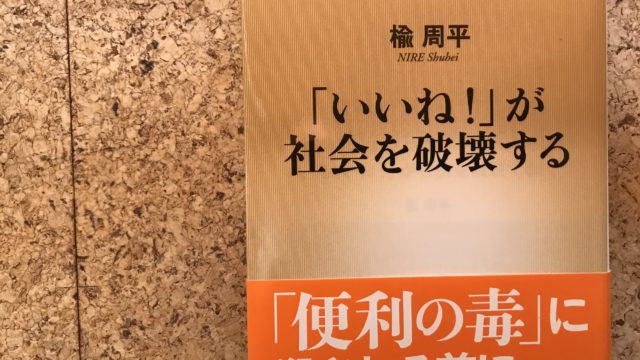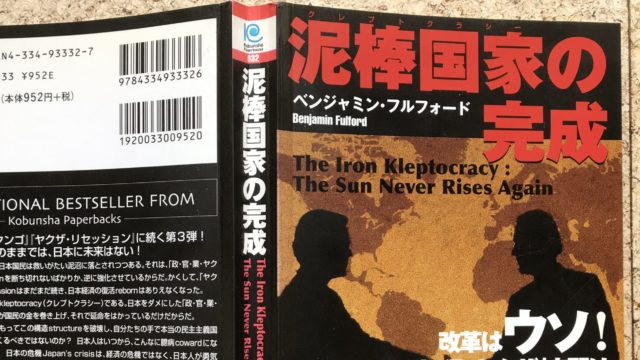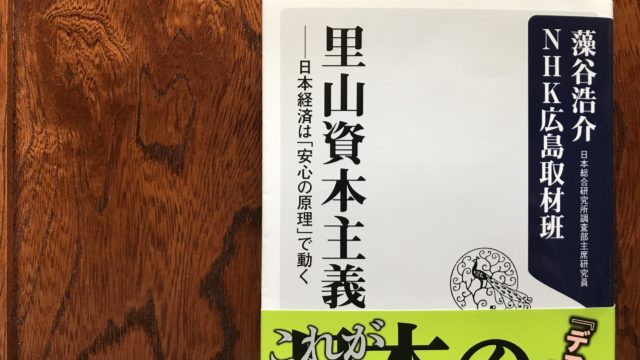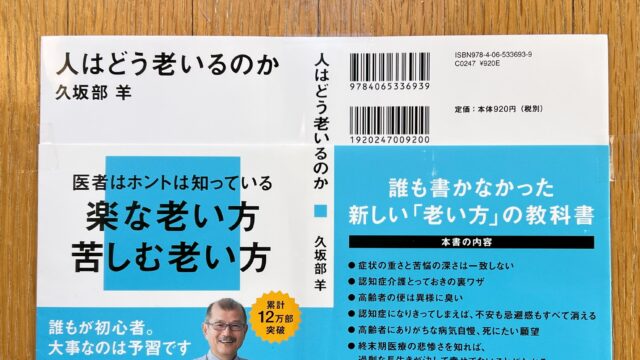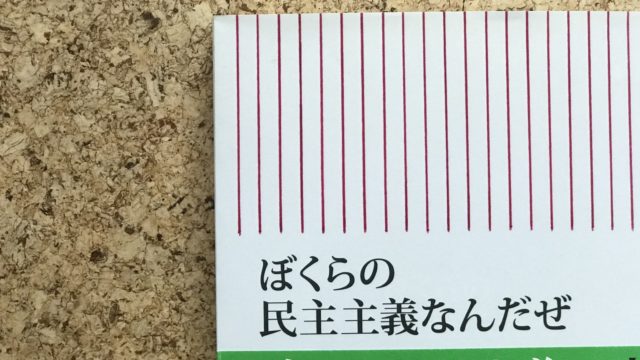とがる言葉 深刻な危機感か ぼくの退化か
(徳間書店、2015年2月)
白井聡氏の『永続敗戦論』(2013年3月)を昨年秋に読んでその着眼に驚いた。その本の帯に推薦文を寄せていたのが、27歳も年上の内田樹氏だった。こちらは『日本辺境論』(2009年)や『街場のメディア論』(2010年)でぼくが衝撃を受けた論客だ。そのふたりの対談である。

読み進めながらまず驚いたのは、その内容よりも、繰り出す言葉の荒っぽさだった。戦後の日本の政治・外交を侮蔑し、安倍政権を見下している感じが著作よりも強く出ている。活字にして書く場合よりも、対談の話し言葉は、とげとげしく、きつく、断定調になっているように思えた。
しかしあとがきで内田氏は、朝日新聞の記事を念頭に「定型に堕す書き手」「手あかのついた言い回しを多用する」と評し、「(この本では)ふたりともそれぞれに『言葉の使い方』にずいぶん気を配っている」と記している。
言論界の最前線にいる論客が気配りした上の発言とすると、ぼくが「荒っぽい」と感じた理由は次のどちらかだろう。日本の政治・社会についてのふたりの危機感がぼくには想像できないほど深刻であるか、ぼくの言語感覚が「定型に堕す書き手」の世界で飼いならされてしまったか、である。両方かもしれない。
そのうえでいちばん印象に残ったのは以下の指摘である。忘備録を兼ねて。知らないことばかり。ぼくはまだまだ勉強が足りない。
■司馬遼太郎の『この国のかたち』の40年説と旧賊軍
- 明治維新から日露戦争(1968~1905)
坂の上の雲』めざした向日葵時代 - 陸軍参謀本部が支配した魔の40年(1905~1945)
戊辰戦争から40年続いた「賊軍・東北差別」が生んだ「嫡出子」
戊辰戦争の敗戦の否認、明治レジームからの脱却を企てた - もとのまっとうな国 (1945~1985 )
■賊軍のルサンチマン(恨みつらみ)が日本軍を暴走させた
1968年(慶応4年/明治元年、干支では戊辰=ぼしん)の戊辰戦争は官軍(新政府軍・薩長)と賊軍(旧幕府勢力+奥羽越列藩同盟)の戦いだった。勝った官軍の薩長は明治軍を仕切るが、1922年に山形有朋、1929年に田仲義一が死んで長州支配は終わる。変わって旧賊軍の奥羽越列藩出身者が台頭してくる。東条英機(岩手)、石原莞爾(庄内)、板垣征四郎(岩手)…。薩長が作り上げた明治システムへの無意識的な憎しみがないと、太平洋戦争であそこ(破滅が予測できる段階)まで突っ込んでいけない…。
■フランスは戦時中のヴィシー政権が独ナチスに加担していた。
第二次大戦では戦勝国とされているのは終戦直前のド・ゴールの力業があったから。ヴィシー政権の官僚たちが横滑りで戦後も残ったことが、フランスではタブー扱いされてきた。
■安倍首相はおそらく人格解離している
周りの人に訊くと、とてもよい人で優しく人の話もよく聞いて穏やからしい。しかし政治家になると別人になる。演劇的に構築されたバーチャルキャラクター。言葉に「葛藤」がない。生身の人間が発する言葉ならもっとノイズがある…。